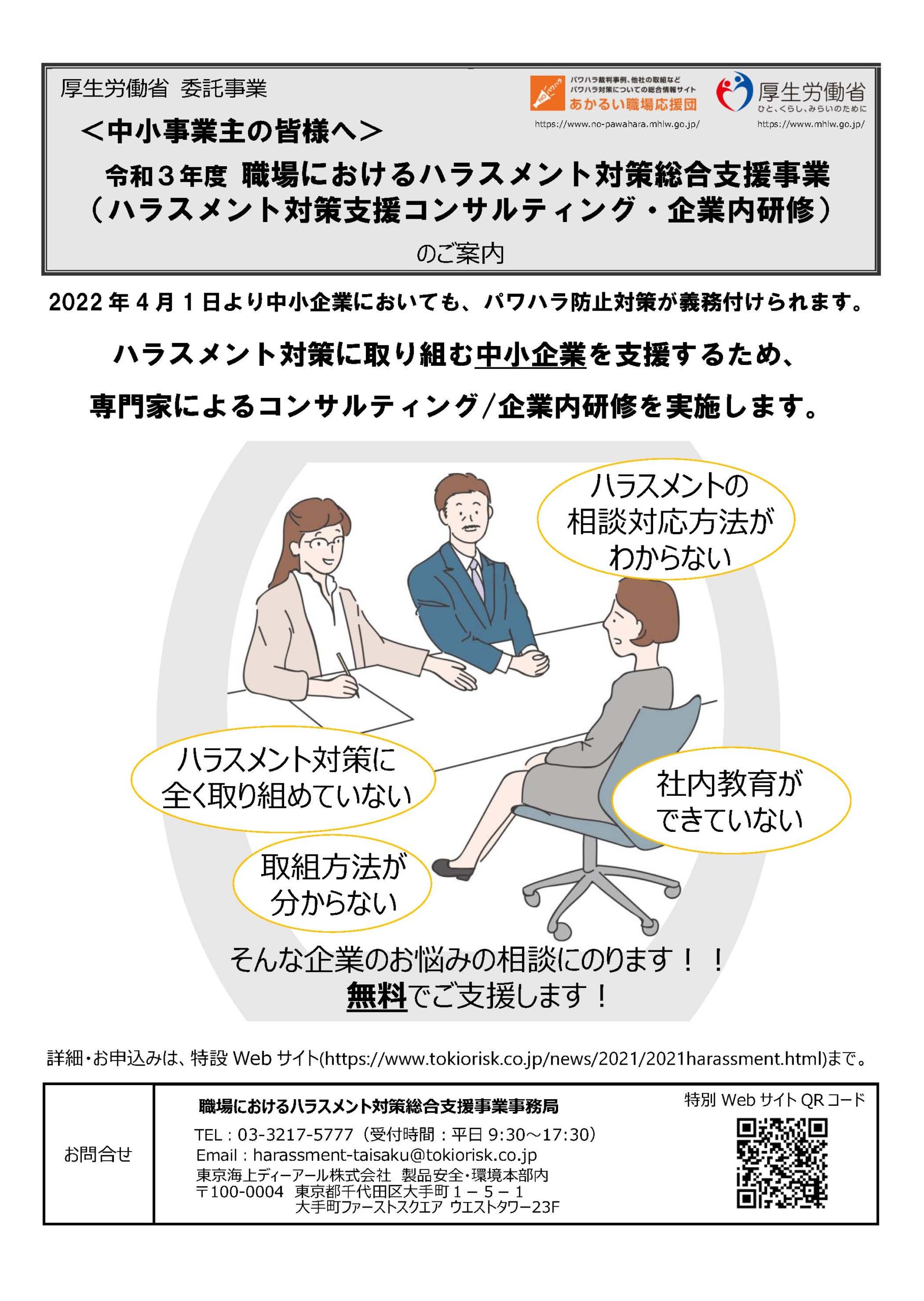ある日、いつものように出社していた50代のAさんは上司に会議室へ呼び出されます。「実は会社として早期退職の制度を設けることになり、あなたは対象者に選ばれました。ぜひ前向きにご検討いただきたい」――静かな口調でしたが、突然の話にAさんは思わず息をのんでしまいます。まだ働き続けるつもりだった自分に対する突然の退職の誘い。どうすればよいのか、断っても不利益があるのではないか、不安が心に広がります。
このような早期退職の勧誘は、会社の業績が思わしくないときに繰り返されてきました。しかし、最近では三菱電機の「黒字リストラ」が報道されたように、業績が好調な時でも事業構造の転換や人員構成見直しのために早期退職募集を行う例も見られるようになってきました。
大手企業でも、社員に対して自発的な退職を提案する場面が日常化しており、今やどの業界・職種でも他人事ではなくなりつつあります。
退職勧奨――「断る権利」はあなたにあります
もしAさんのように会社から早期退職を打診、つまり退職勧奨されたとしたら、まず知っておくべきなのは、退職勧奨と解雇の違いです。
退職勧奨は、会社側から「もしよければ、会社を円満に辞めませんか?」と提案されるものであり、社員本人がその提案に同意するかどうかを自由に決めることができます。つまり、退職するか否かの最終的な決定権は、企業ではなく社員側にあるのです。
会社から強制されることはありませんし、断ったからといって不利益な扱いを受ける理由もありません。会社が提示する退職条件に納得できなければ、その場で「辞めません」と意思表示して問題ありません。
一方で解雇とは、会社が一方的な意思によって労働契約を終了させるもので、社員本人が働き続けたいと言ったとしても、強制的に離職させられます。
日本の法律では、解雇には非常に厳しい制限が課されています。労働契約法第16条では「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ解雇無効と明記されていますし、不当・理不尽な解雇は訴訟によって取り消されることもあります。会社が「業績が悪いから」「年齢が高いから」などといった曖昧な理由だけで自由に解雇できるものではありません。
会社から「辞めてほしい」と言われたら、解雇だと思い込んでしまう人がいますが、会社も解雇が難しいことは理解しているので、通常は退職勧奨を試みます。解雇なのか退職勧奨なのか、しっかり確認しておきましょう。
会社が退職勧奨をすること自体は違法ではありませんが、同意を強く迫られたり、拒否を理由に不当な扱いを受けたりする場合には、違法な行為に該当する可能性があります。
違法となる退職勧奨――どんな場合に問題になるのか
では、どのような場合に退職勧奨が違法になるのでしょうか。
裁判所は、退職勧奨の「方法・内容・回数・期間・態度」などを総合的に見て、社会通念上許容される範囲を逸脱していないかを判断します。
例えば、次のようなケースが問題となります。
- 執拗な面談がくりかえされ、断っても呼び出しが続く
- 精神的な圧力や将来の不利益を強調し、不安にさせる
- 名誉や人格を否定する発言がある
- 配置転換や職務内容の大幅な変更をちらつかせて迫る
- 本人の意思を全く尊重せず、一方的に退職を求め続ける
実際に違法と認定された判例として、日本アイ・ビー・エム事件(東京地裁平成23年12月28日判決)があります。「度重なる面談に加え、能力や人格を否定する発言を繰り返した」「会社への貢献を全否定し将来への不安を過度に煽った」ことなどが、本人の自由な意思形成を著しく妨げたと裁判所は認定し、違法性を認めています。単なる退職の促しを超えて精神的な圧迫や威迫となった場合、合意書があったとしてもその効力が否定される点が現代的な特徴です。
実際に退職勧奨を受けたら
もし冒頭のAさんのように、突然会社から早期退職を打診された場合、大切なのは落ち着いて状況を把握することです。必要であれば、説明内容をメモしたり、再度説明を求めたりすることも遠慮なく行いましょう。
加えて、会社から提示された具体的な退職条件を詳細に確認することも欠かせません。退職金の上積みがあるのか、再就職のための支援や相談窓口が設けられているのか、など、会社によって条件は大きく異なります。これらの支援内容が十分でなく不透明な点があれば、納得できるまで質問しましょう。
今後の人生やキャリアに大きく影響することですから、軽々しく自分だけで即答せず、家族や外部の専門家に相談するために、一度持ち帰って検討することをおすすめします。
キャリアの総仕上げをどうするか
早期退職の誘いがあったとき、「会社に求められているなら応じるべきなのか」「断って立場が悪くなったらどうしよう」と迷う方は少なくありません。しかし、退職勧奨はあくまで選択肢のひとつであり、必ずしも応じなければならないものではありません。
あなたには断る権利があり、断ったからと言って会社から不利益取り扱いを受けたり、人格否定や脅しのような発言があると、損害賠償など企業側の責任が問われることになります。
退職するかどうかを検討する際は、単に金銭や支援策といった条件で決めるのでなく、ご自身のキャリアをどのように総仕上げしたいかも、じっくり考えてほしいのです。
目先の条件や周囲の空気に流されるのではなく、「いまのタイミングで退職することが本当に自分にとって最善なのか」「この先もう一度別の形で社会に貢献したいことはないか」「今の職場でもう少しチャレンジしてみたい目標はないだろうか」といった視点から中長期的に判断することが重要です。
不安や疑問がある場合、すべてを自分ひとりで解決しようとしないでください。社内にある人事窓口やコンプライアンス担当、あるいは社会保険労務士や弁護士といった外部の専門家、さらに労働組合や公的相談窓口なども、心強い味方になってくれます。第三者に相談することで、ご自身の考えが整理されるだけでなく、新たな視点が見えてくることもよくあります。大切なキャリアの岐路を迎えるこの場面で、納得できる決断ができるよう、遠慮せず適切なサポートや専門的な意見を活用してください。
自分の人生や働き方をどう締めくくるかは、誰にとっても大切な選択です。会社の都合だけでなく、ご自身のこれまでの努力や今後の人生設計にも十分目を向けて、じっくり総合的に決断してください。そのうえでの選択なら、たとえどんな結果でも、きっと新しい一歩になるはずです。