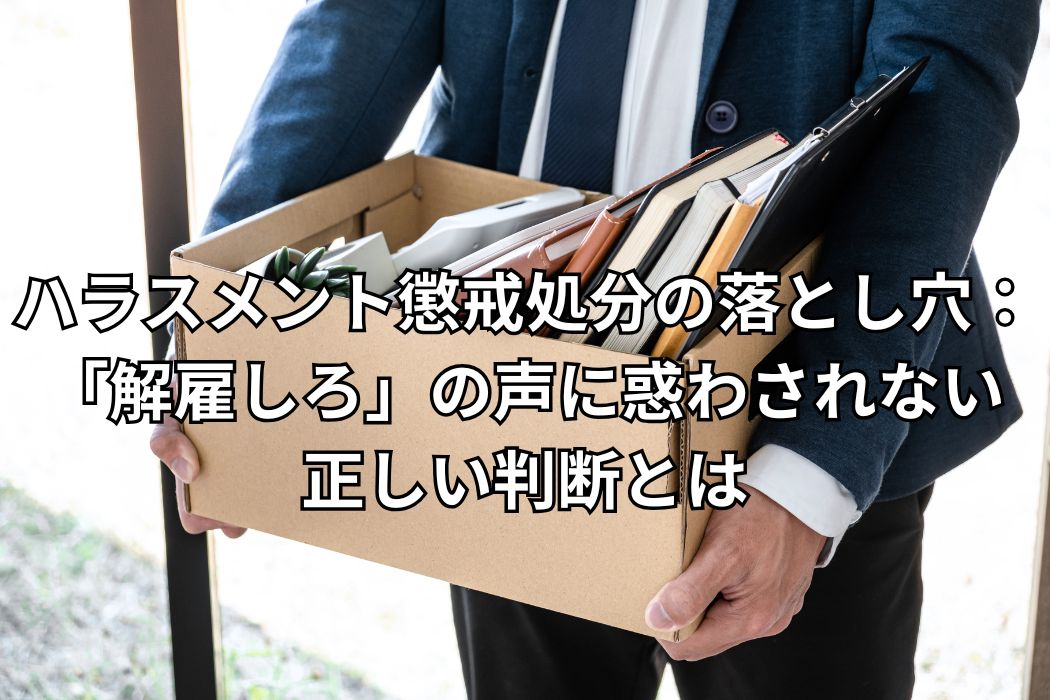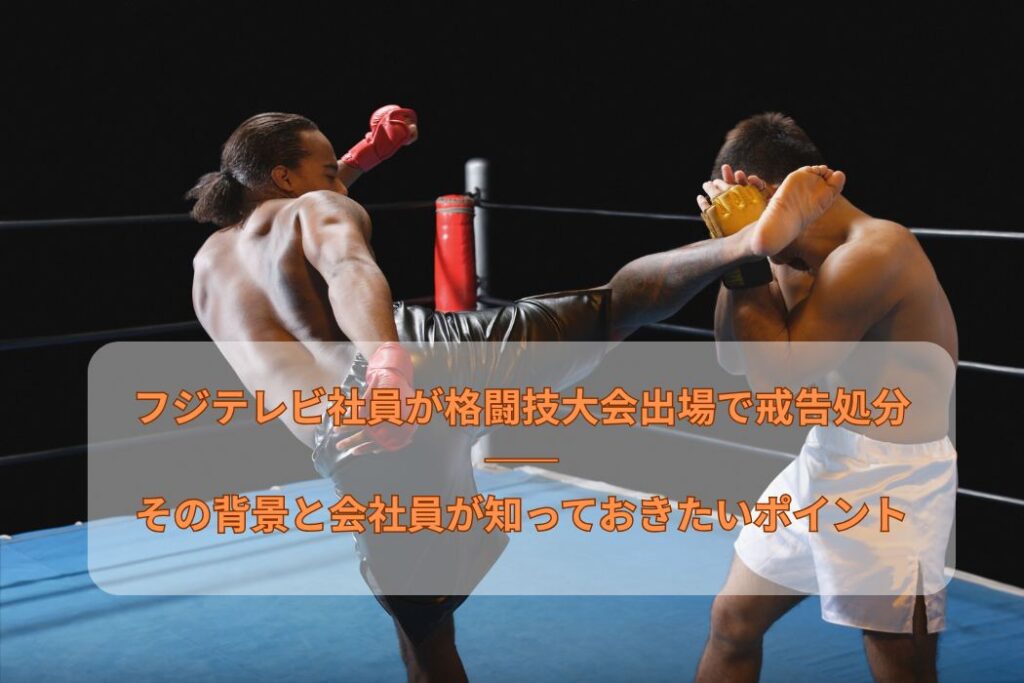
2025年4月末、現役フジテレビ社員で格闘家としても活動するウザ強ヨシヤさんが、東京ドームで開催される格闘技イベント「RIZIN男祭り」への出場を巡り、勤務先のフジテレビから戒告処分を受けたことがニュースになりました。この件は、会社員が私生活でスポーツや副業に取り組む際、会社側がどのような対応を取れるのかという点で、多くの方にとって他人事ではありません。
社員の私生活と会社の規制―どこまで許される?
社員の私生活上のイベントを会社はどこまで規制できるのでしょうか。また、違反時に懲戒処分を課すことができるのでしょうか。
ウザ強ヨシヤさんは、2024年10月に行われた格闘技イベント「FIGHT CLUB.2」への出場についてフジテレビに申請していましたが、会社側は許可を出しませんでした。その後も格闘技活動を続け、2025年5月4日に開催される「RIZIN男祭り」への参戦が発表されると、フジテレビは戒告という懲戒処分を下しました。さらに、今後も許可なく大会に出場した場合は、より重い処分の可能性も示唆されています。
このニュースを受け、「格闘家である前に社員なのだから、会社が就業規則で決めたことであれば守るのが当たり前」と感じる人もいれば、「自分の休日の過ごし方まで会社が口を出せるの?」と疑問に思う人もいるしょう。実際、副業については許可制にしたり、なんらかの規制をしている会社も多いのですが、副業やスポーツ大会への出場は、あくまでも社員の私生活です。会社が社員に指揮命令できるのは業務についてだけです。いくら就業規則に定めていようとも、会社が社員の私生活に制限なく口を出せるわけではありません。
会社員の私生活に対する会社の関与は、判例でも慎重に判断されています。
会社が社員の私生活上の行為を理由に懲戒処分を科すことができるかについて、重要な指針となるのが日本鋼管事件(最高裁昭和49年3月15日判決)です。
この事件では、社員が私生活で刑事特別法違反により罰金刑を受けたことを理由に懲戒解雇されましたが、最高裁は「会社の社会的評価に重大な悪影響があったとはいえない」として懲戒解雇を無効と判断しました。
昭和49年というと、ずいぶん前だな、と思う人も多いかもしれません。しかし、社員の私生活上の行為については、「会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合に限り、懲戒処分が認められる」というこの判決の考え方は、現在に至っても社員の私生活と会社の規制についての基本的な枠組みとなっています。
一般企業とメディア企業の違い
今回の事件はフジテレビというメディア企業で起こったことですが、一般的な企業の場合、社員の私生活や副業は本来自由です。スポーツや趣味、地域活動などに会社が介入することは基本的にできません。
ただし、次のような場合は例外となります。
- その活動が本業に重大な支障を及ぼす恐れがある場合(例:疲れや怪我によって仕事に差し支える)
- 会社の信用やイメージを著しく損なう行為がある場合(例:暴力事件や反社会的勢力との関与)
- 会社の機密情報漏洩や競業にあたる場合
こうした場合、就業規則に「会社の許可なく副業や一定の活動を行ってはならない」といった規定を設け、違反時には懲戒処分を科すことが認められることがあります。ただし、規制の範囲や処分の重さは一般常識で考えて合理的である必要があり、過度な制限は無効と判断されるリスクもあります。
一方、フジテレビのようなメディア企業では、社員の私的活動が会社のブランドや社会的信用と直結しやすいという特殊事情があります。テレビ局の社員が格闘技大会に出場し、その様子が広く報道されることで、会社のイメージや放送倫理に影響が及ぶ可能性があるからです。
このため、メディア企業では「業務に支障をきたす恐れがある活動」「会社の名誉や信用を損なうおそれがある活動」については、就業規則で事前申請や許可制を設けるケースが多くなります。今回の事例も、会社側が「業務や会社のイメージへの影響」を重視し、申請に許可を出さず、さらに無断出場に対して戒告処分を下したものと考えられます。
懲戒処分の有効性
就業規則に禁止規定があったとしても、それだけで自動的に懲戒処分が有効になるわけではありません。実際に懲戒を行うには、法的にも判例上も、いくつかの厳密な条件を満たす必要があります。主なポイントは次の4つです。
1. 就業規則に根拠規定があり、周知されていること
まず、どんな行為が懲戒の対象になるか、就業規則にきちんと書かれていることが必要です。また、その内容が社員にしっかり伝わっていることも大切です。たとえば、社内掲示やイントラネットなどで、誰でも確認できる状態にしておくことが求められます。
2. 懲戒事由に該当する事実があること
実際にその禁止規定に違反した、という事実がなければなりません。会社側は、何が起きたのかを客観的な証拠で示す必要があります。曖昧なまま処分することはできません。
3. 処分の重さが社会通念上相当であること
違反があったとしても、処分が重すぎては認められません。たとえば、ちょっとしたミスでいきなり解雇、というのは行き過ぎです。行為の内容や悪質性に見合った処分かどうかがポイントになります。
4. 適正な手続きが踏まれていること
最後に、事実確認や本人への説明、弁明の機会をきちんと設けるなど、手続きが公正に行われていることが必要です。手続きがずさんだと、処分自体が無効になることもあります。
これらの条件がそろって初めて、懲戒処分は有効と認められます。
私生活の自由と会社の秩序のバランス
今回のフジテレビ社員の戒告処分は、メディア企業ならではの特殊性と、会社員の私生活に対する規制のあり方を考えるうえで、非常に示唆に富む事例です。このケースから読み取れるのは、「社員の私生活の自由」と「会社の秩序維持・信用保護」という二つの価値観のバランスが、現代の職場ではより重要になっているということです。
まず、社員の私生活は原則として個人の自由であり、会社が過度に干渉することはできません。たとえば、休日の過ごし方や趣味、スポーツ活動などは本来自由に選択できるものであり、会社が一方的に制限したり監視したりすることは、パワハラやプライバシー侵害と評価されることもあります。
しかし一方で、社員の私生活上の行為が会社の信用やイメージ、業務運営に直接的な悪影響を及ぼす場合には、会社が一定の規制を設けたり、場合によっては懲戒処分を行うことも法的に認められることがあります。たとえば、社会的に問題視されるような犯罪行為や、SNSでの不適切な発信などがこれに該当します。
社員の立場からは、「自分の活動が会社にどんな影響を与えうるか」を冷静に考え、会社のルールや申請手続きをしっかり確認し、必要な場合は事前に相談・申請することが大切です。特に、勤務先の就業規則や副業規定、SNS利用ガイドラインなどを一度見直してみるとよいでしょう。
一方、会社側も社員の自己実現や健康増進のための活動を一律に制限するのではなく、どのような場合にリスクが現実化しうるのかを具体的に見極め、合理的なルール運用を心がける必要があります。行き過ぎた規制は、社員のモチベーション低下やパワハラ認定につながるリスクもあります。
自分の自由と会社の秩序、その両方を尊重する姿勢が、現代の働き方には求められています。