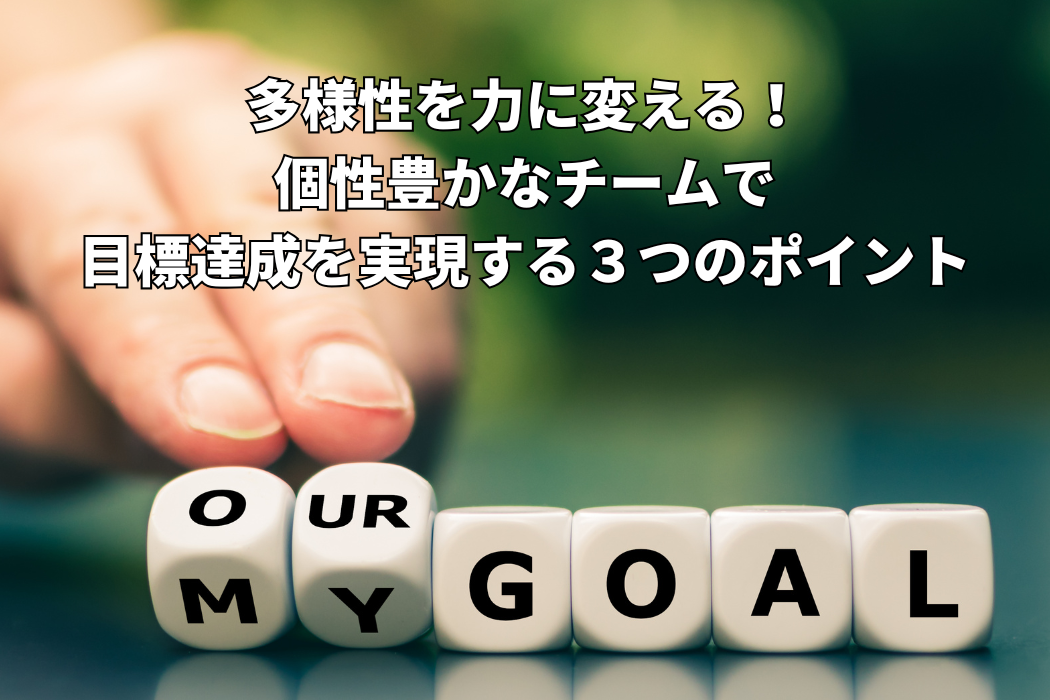最近、Helpfeelが実施した「カスハラの認識」に関する調査結果が発表されました。この調査は2025年3月に北海道・東北、関東、中部、関西、九州地方に住む20代〜60代の男女1,070名を対象に行われたものです。
この調査で特に注目すべき点は、「注文した商品が出てくるのが遅かったと指摘すること」「店員に『もっと安くならないか』と値引き交渉をする」「店員に『おまけをつけてくれないか』と伝える」行為については、若年層ほどカスハラと捉える傾向が見られたことです。
この結果から、対等な立場で要望を出し、双方の都合をすりあわせて着地点を決めるという考え方が、特に若年層に根付いていないことがわかります。
これは、障害者からの要望をカスハラととらえてしまう素地になっており、早急に適切な線引きを事業者で決めないと、合理的配慮という考え方が絵に描いた餅になってしまう恐れがあります。
カスハラと合理的配慮の違い
まず、カスタマーハラスメント(カスハラ)とは何でしょうか。
厚生労働省の「カスタマーハラスメント企業対策マニュアル」に基づけば、「顧客や取引先からの要求の内容の妥当性に照らして、その要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、当該手段・態様により従業員の就業環境が害されるもの」と定義されています。
東京都カスハラ防止条例でも、カスハラは「顧客等による著しい迷惑行為が就業者の人格又は尊厳を侵害する等就業環境を害し、事業者の事業の継続に影響を及ぼすもの」とされています。
要するに、相手(企業、店舗)の都合におかまいなしに、ただ自分の要求をつきつけ、それがかなえられないと常識からはありえないような暴力的(肉体的な暴力だけでなく精神的なものも含む)な行動をとる、それがカスハラです。
顧客という立場を強い立場と位置づけているので、企業や店舗とは対等ではないという考えが根底にあります。
一方、合理的配慮とは、障害者差別解消法に基づき、「障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」というものです。
この社会は障害がないということを前提に設計されているので、障害がない人がふつうに受け取っているさまざまな利便性が障害者にはバリアになってしまいます。
障害者差別解消法は、このバリアを少しでも取り除こうという趣旨です。
合理的配慮とは、障害者から要望があれば、なにがなんでもそれをかなえなければならないというものではありません。
定められているのは「負担が重すぎない範囲で対応すること」で、むりな場合は断ってもよいのです。
ただ、なにも考えずに「いままでやったことがないから」という理由で断るのではなく、要望を出した障害者と対話して、ニーズが満たされる別の方法を考える等、なんらかのアクションをしてくださいということです。
対等な立場での対話が前提となっているのです。
| カスタマーハラスメント(カスハラ) | 合理的配慮 | |
|---|---|---|
| 定義 | 顧客や取引先からの要求が社会通念上不相当であり、それによって従業員の就業環境が害される行為 | 障害者差別解消法に基づき、負担が過重でない範囲で社会的障壁を除去するために必要な配慮を行うこと |
| 例 | 暴言、過度な要求、威圧的な態度 | 車いす使用者への移動支援、筆談対応など |
| 特徴 | – 顧客が強い立場を利用して企業や店舗の都合を無視 – 対等な関係を前提としない | – 障害者との対等な立場での対話が前提 – 要望に対して可能な範囲で対応する |
若年層のカスハラ認識と合理的配慮との混同リスク
調査によると、若年層は「値引き交渉」や「おまけをつけてほしい」といった要望をカスハラと捉える傾向が強いことが明らかになりました。これは、若年層が顧客と店員の関係を対等なものとして捉えるよりも、一方的なサービス提供の関係、つまり「顧客になにか言われたらイヤでも対応しなくてはならない、不快な体験」として理解している可能性を示しています。
顧客からのなんらかの要望があったとしても、対応できないものであればその旨説明して断ればよいことなのですが、「できないと説明する」「断る」ということを、大きな心理的負担と捉えていることが想像できます。
2024年4月から、障害者差別解消法の改正により、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました。
これにより、車いす使用者への移動支援や聴覚障害者とのコミュニケーション支援など、障害のある顧客のニーズに、できる範囲で応える必要があります。
しかし、今回の調査結果に見られる若年層のカスハラに対する捉え方は、障害者からの配慮の要請を「無理な要求」と誤解してしまう可能性を示唆しています。
例えば、車いす使用者が高い棚の商品を取ってほしいと頼むことや、聴覚障害者が筆談を求めることなどが、カスハラと混同されてしまう恐れがあります。
「要望を伝えられること」自体を不快に感じるような気持ちを持って接客していると、要望を伝えた障害者に対して「カスハラ客」であるという認識で対応してしまうことになります。
実際に困りごとを解消できない障害者側はもちろん、店員の側も、通常の要望を受けるだけで不快になりますから、互いにとって不幸な状態ではないでしょうか。
全国に広がるカスハラへの取り組み
2025年は「カスハラ防止条例元年」とも言われるように、全国で条例制定の動きが加速しています。
東京都では2024年10月に全国初となる「東京都カスタマーハラスメント防止条例」が制定され、北海道議会も同年11月にカスハラ防止条例を可決・成立させ、いずれも2025年4月から施行されます。
三重県桑名市は全国の市町村で初めてとなるカスハラ防止条例を制定し、悪質なカスハラを繰り返した場合に氏名を公表するという踏み込んだ制裁措置を盛り込みました。
また、愛知県、埼玉県、大阪府、長崎県佐世保市、熊本県、青森県、富山県、栃木県、鹿児島県などもカスハラ対策マニュアルの策定や実態調査を進めており、青森県は2025年度から県庁の外線電話の通話録音を開始する計画で、職員の被害防止を目的に3364万円の予算を計上しています。
先進的な企業の取組も、たびたび報道されています。
楽天グループは2023年10月に「カスタマーハラスメントポリシー」を制定し、カスハラに該当する行為を明確に定義しています。
このポリシーでは「個々の従業員に対する過度な要求や攻撃」「楽天グループが提供するサービスや商品以外の要求」「不合理な金銭要求」「実現不可能な要求」などをカスハラと定義し、従業員が適切に対応できるよう指針を示しています。
また、カスハラが発生した場合の対応フローも明確化しており、従業員の安全を最優先に考えた体制を構築しています。
ホテルニッコー奈良は「カスタマーハラスメントに関する基本方針」を策定し、「カスタマーハラスメントに該当する行為に対しては、合理的な話し合いを通じて適切な解決策を模索し、より良い関係構築を目指します」という姿勢を明確にしています。
同ホテルでは従業員教育にも力を入れており、カスハラの事例研究や対応訓練を定期的に実施することで、実際の場面での適切な対応力を高めています。さらに、カスハラが発生した際の報告体制や心理的ケアの仕組みも整備し、従業員が安心して働ける環境づくりに取り組んでいます。
このような動きは、働く人からすると「カスハラから守ってもらえる」よいことです。
しかし、会社が従業員教育をきちんとやっていない状態で、マスコミ情報だけを受け取ってしまうと、「自分が不快であればなんでもカスハラ」と考える就業者を増やす要因ともなります。
事業者に求められる適切な線引き
このような自治体や先進企業の動きを踏まえ、事業者には以下のような対応が求められます:
- 明確な基準の策定: カスハラと合理的配慮の違いを明確にした社内ガイドラインを作成する。
- 従業員教育の徹底: 特に若年層の従業員に対して、合理的配慮の重要性と、それがカスハラとどう異なるかを教育する。
- 建設的対話の促進: 障害のある顧客とのコミュニケーションを「建設的対話」として捉え、双方が納得できる解決策を模索する姿勢を持つ。
- 相談体制の整備: 従業員が判断に迷った場合に相談できる体制を整え、適切な対応を支援する。
東京都や北海道では2025年4月にカスタマー・ハラスメント防止条例が施行される予定であり、カスハラは社会全体で取り組むべき課題となっています。
東京都は条例施行前に典型的なカスハラの事例を公表する予定であり、これを参考に各企業は顧客との問題に対処する方法を検討すべきでしょう。
対等な関係構築のために
最終的に目指すべきは、顧客と事業者が対等な立場で、互いの尊厳を尊重しながら関係を構築することです。
カスハラを防止しつつも、合理的配慮を適切に提供するためには、双方の対話と相互理解が不可欠です。
今後、事業者や企業は働く従業員保護のためのカスハラ防止と対策を行う義務が課せられる流れとなっています。
障害のある人もない人も共に生きる社会を構築するためには、カスハラと合理的配慮の違いを明確にし、適切な対応を取ることが重要です。
特に若年層に対しては、顧客と事業者の対等な関係性や、合理的配慮の意義について教育を行うことが必要でしょう。
従業員教育を通して、顧客とのコミュニケーションを「心理的負担」「コスト」ととらえるのではなく、対等な対話を通じて、よりよいサービスや、ひいてはよりよい社会が構築できるのだという価値観を共有してもらいたいのです。
そのためには、理念だけを伝えるのではなく、傾聴やアサーションのようなコミュニケーション・スキルを身につける研修を行い、自分のためにも相手のためにもなり、不快な体験も減るということを実感してもらうのがよい方法でしょう。
改正障害者差別解消法の施行と各自治体のカスハラ防止条例の制定により、「障害のある人が他の人と同じように生活できる社会」と「就業者が安心して働ける環境」の両立が目指されています。
この理念を実現するためには、カスハラという概念に過度に敏感になるのではなく、建設的な対話を通じて互いのニーズを調整する文化を育てていくことが大切です。