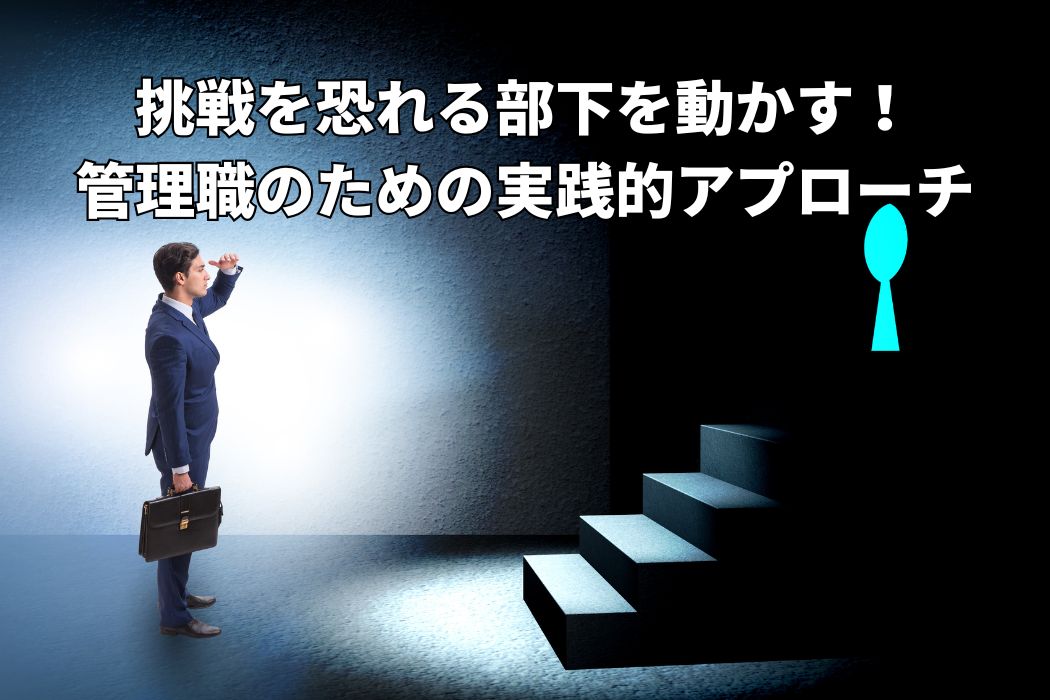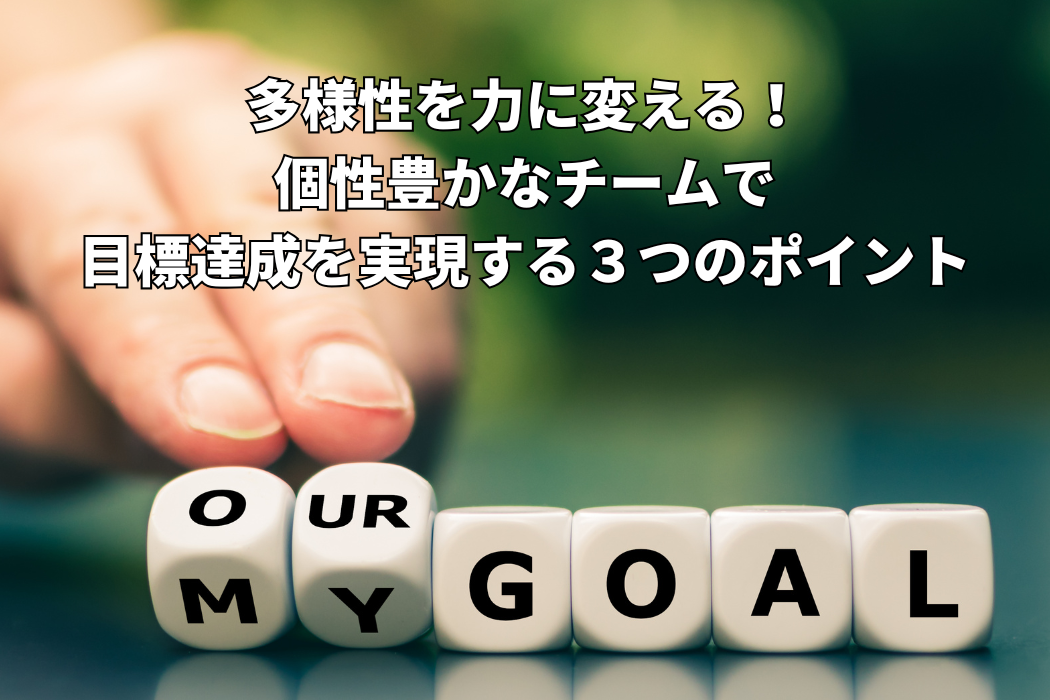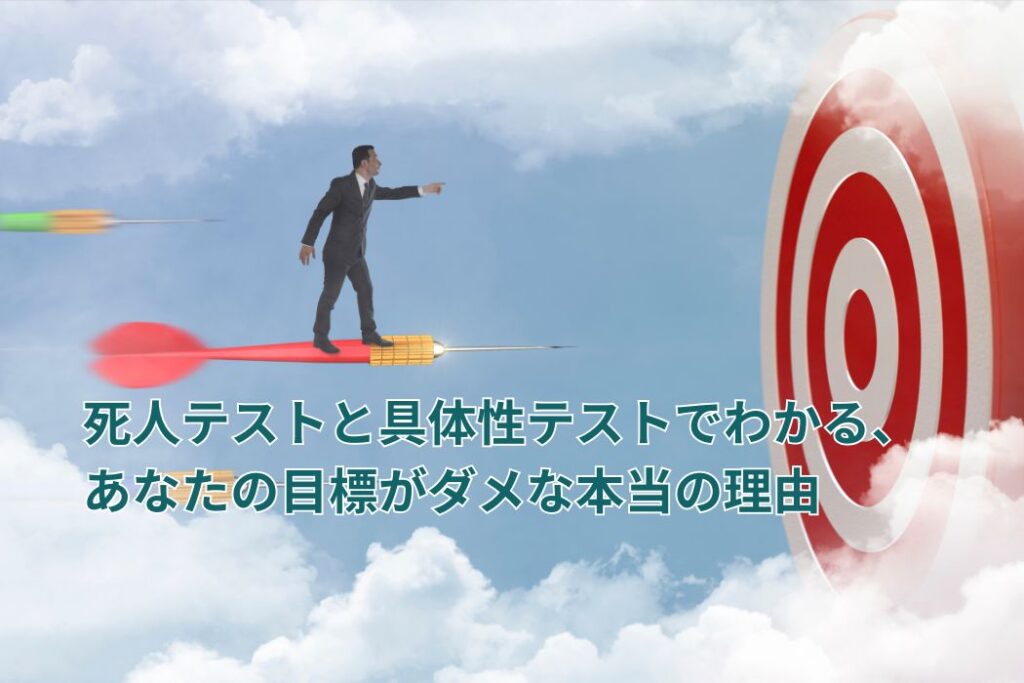
目標設定は人生の様々な場面で重要ですが、せっかく目標を立てても達成できないことがあります。
その原因の一つに「目標の立て方」があります。
実は目標を立てる時点で、達成可能性が高いかどうか、判断できてしまうのです。
今回は行動分析学の基礎概念である「死人テスト」と「具体性テスト」を活用した効果的な目標設定の方法についてご紹介します。
死人テストとは何か?
「死人テスト」とは、1965年に行動分析学の研究者オージャン・リンズレー(Ogden Lindsley)によって提唱された概念で、「死人でもできることは行動ではない」という行動の定義です。
このテストによると、以下のようなものは「行動」とは見なされません。
- 否定形:「~しない」(例:怒らない、食べない)
- 受け身形:「~される」(例:褒められる、話しかけられる)
- 状態:「~している」(例:黙っている、じっとしている)
これらは死人でもできることなので、行動目標としては不適切なのです。
具体性テストとは何か?
具体性テストとは、目標が十分に具体的かどうかを確認するためのテストです。
後述のSMART目標設定法の「S(Specific:具体的)」の要素に関連しています。
具体性テストの合格基準
具体性テストに合格するためには、以下の基準を満たす必要があります:
- 5W1Hが明確である:Who(誰が)、What(何を)、When(いつ)、Where(どこで)、Why(なぜ)、How(どのように)が明確に定義されている
- 測定可能な要素を含む:数値や割合などの具体的な指標が含まれている
- 行動が明確に特定されている:具体的にどのような行動をとるのかが明示されている
例えば、「ダイエットする」という目標は死人テストには合格しますが、具体性に欠けるため具体性テストには不合格です。
一方、「1ヶ月間、毎日30分のウォーキングを行う」という目標は、具体的な数値と行動が含まれているため具体性テストに合格します。
1ヶ月に1つの目標に絞る重要性
行動変容の研究では、一度に多くの行動を変えようとすると失敗しやすいことが指摘されています。
習慣形成の研究によれば、新しい行動が習慣になるには約21〜30日かかるとされています。
そのため、1ヶ月間は1つの目標に集中することが効果的です。
この考え方が重要な理由は、下の3つです。
- 集中力の維持:複数の目標に取り組むと注意が分散し、どれも中途半端になりがちです
- 習慣形成の時間:新しい行動が習慣になるには一定期間の繰り返しが必要です
- 成功体験の積み重ね:小さな成功を積み重ねることで自己効力感が高まります
多くの方が目標達成に失敗する理由の一つに、「一度に多くのことに取り組もうとする」ことがあります。
一つの目標に集中することで、成功確率が高まります。
死人テストと具体性テストを使った目標設定の方法
1. 否定形を肯定形に変換する(死人テスト)
まず、否定形で表現された目標を肯定形に変換します。
不適切な目標例:
- 「お菓子を食べない」→死人でもできる
- 「遅刻しない」→死人でもできる
適切な目標例:
- 「お菓子を食べたくなったら、果物を食べる」
- 「会議の10分前に会議室に到着する」
2. 具体性を高める(具体性テスト)
死人テストをパスした目標に、SMART基準を適用して具体性を高めます。
SMART基準(1981年にジョージ・T・ドーランが提唱):
- Specific(具体的):5W1Hが明確である
- Measurable(測定可能):数値化できる
- Achievable(達成可能):実現可能である
- Relevant(関連性):自分の価値観や大きな目標と関連している
- Time-bound(期限付き):期限が設定されている
3. 目標を絞る
具体的になった目標の中から、今月取り組む1つの目標に絞ります。
両テストを組み合わせた目標設定の実践例
例1:朝の習慣改善
不適切な目標:「朝寝坊しない」(死人テスト不合格)
改善した目標:「朝起きる」(死人テスト合格、具体性テスト不合格)
両テスト合格の目標:「今月の平日は6時30分にアラームが鳴ったら、すぐにベッドから体を起こす」
- 具体性:いつ(今月の平日6時30分)、何を(ベッドから体を起こす)、どのように(すぐに)が明確
- 期間:1ヶ月間の単一目標
例2:仕事の生産性向上
不適切な目標:「仕事中にサボらない」(死人テスト不合格)
改善した目標:「集中して仕事をする」(死人テスト合格、具体性テスト不合格)
両テスト合格の目標:「今月の平日、午前中に25分間の集中作業を3回行う」
- 具体性:いつ(今月の平日午前中)、何を(集中作業)、どのように(25分×3回)が明確
- 期間:1ヶ月間の単一目標
例3:健康的な生活習慣
不適切な目標:「不健康な食事をしない」(死人テスト不合格)
改善した目標:「健康的な食事をする」(死人テスト合格、具体性テスト不合格)
両テスト合格の目標:「今月、毎食に野菜を一皿追加する」
- 具体性:いつ(今月の毎食)、何を(野菜一皿)、どのように(追加する)が明確
- 期間:1ヶ月間の単一目標
目標設定のコツ
- 小さく始める:達成可能な小さな目標から始めましょう
- 1ヶ月に1つの目標に絞る:集中力を分散させず、習慣形成を促進します
- 数値化する:「週に3回」「10分間」など、できるだけ数値を含めると測定しやすくなります
- 環境を整える:目標達成をサポートする環境を整えましょう
- 記録する:行動の記録をつけることで、進捗を確認できます
- 次の目標は前の目標が習慣化してから:一つの行動が習慣になってから次の目標に進みましょう
成功事例
ある企業の研修で「1ヶ月1目標」を実践した結果、以下のような成功事例がありました。
- Aさん(営業部課長):「毎朝、出社後に部下全員に挨拶をする」という目標を1ヶ月続けた結果、以前より小さな問題も気軽に相談されるようになりました。部下からは「話しかけやすくなった」という声が聞かれるようになりました。
- Bさん(総務部主任):「毎日18時までに翌日のTo Doリストを3項目作成する」という目標を1ヶ月続けた結果、業務の優先順位が明確になり、残業時間が少し減少。「何から手をつけるべきか迷う時間が減った」と実感しています。
いずれも、シンプルで具体的な1つの行動に絞ったことで、無理なく継続でき、習慣化に成功しています。
大きな変化ではなくても、小さな積み重ねが職場環境の改善につながっています。
まとめ
死人テストと具体性テストは、効果的な目標設定のための強力なツールです。
死人テストで「何をするか」という行動に落とし込み、具体性テストで5W1Hと測定可能な要素を加え、さらに「1ヶ月に1つの目標に絞る」という考え方を適用することで、目標達成の可能性が高まります。
この3つのテストに合格しない目標では、目標を立てた時点で失敗が目に見えていると言えるでしょう。
目標は、達成するためにつくるのです。
その意思がなければ、夢や願望です。
次に目標を設定するときは、これらのテストを活用して、あなたの目標達成力を高めていきましょう。