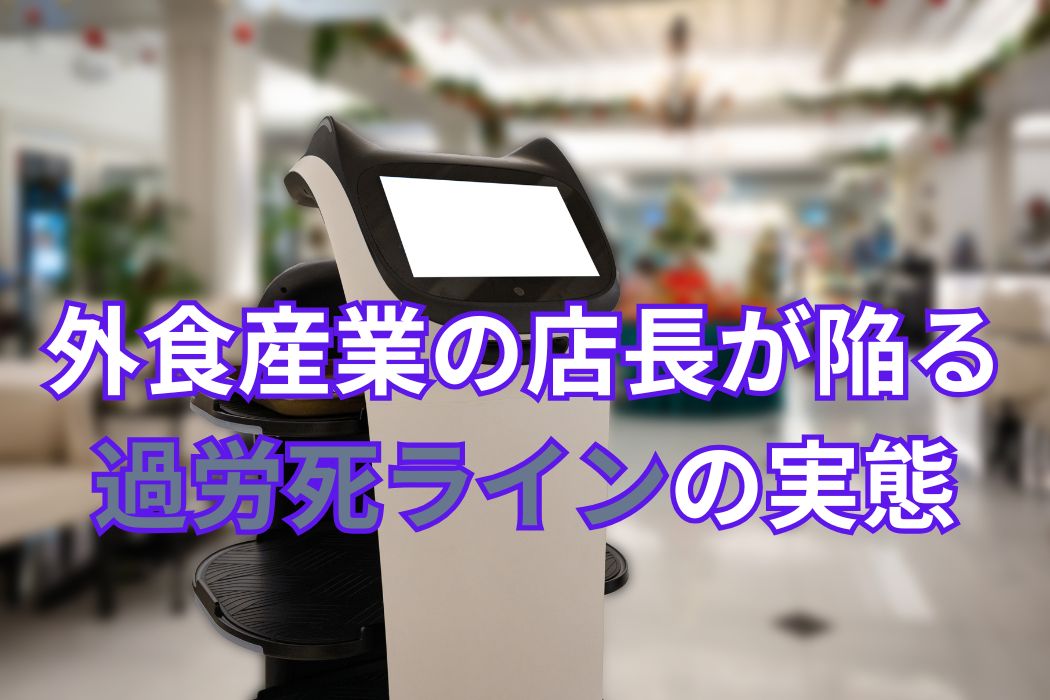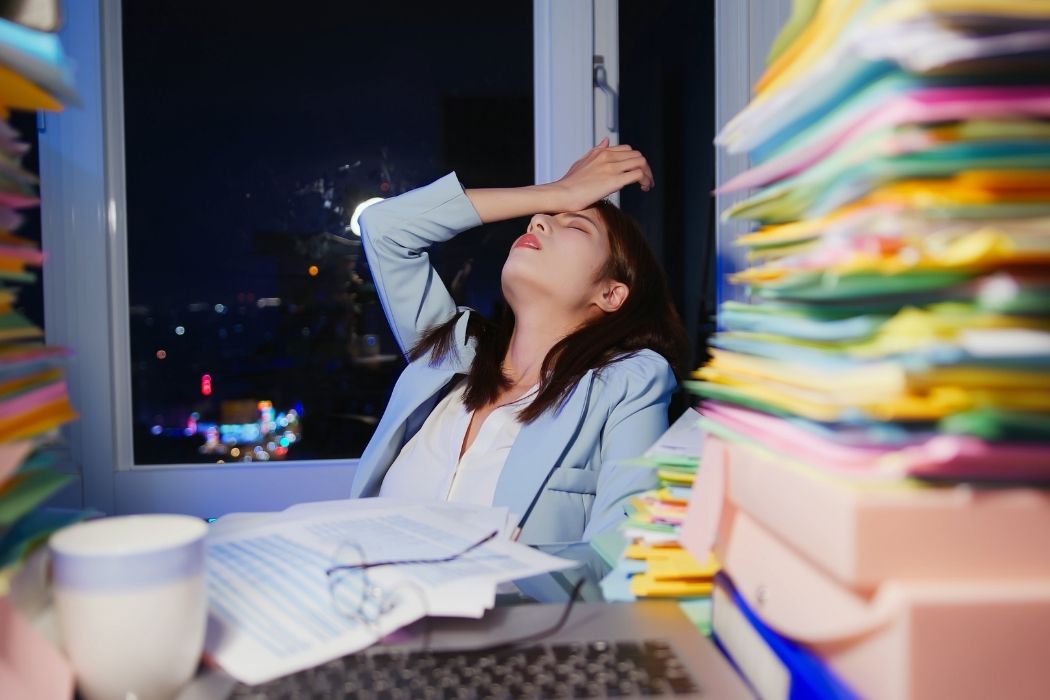今年9月、12年にわたった河合塾講師の雇止め事件の判決が出ました。
業務委託契約だったにもかかわらず、最高裁の決定で「労働者性」が認められ、復職と10年分の賃金(バックペイ)の支払いが河合塾に命じられました。契約の形式と実態で得られる権利・保護の違いを、社会全体が突きつけられた出来事でした。(「河合塾からクビを言い渡された」 50代で失業した講師が最高裁で「労働者性」を勝ち取るまでの12年 弁護士ドットコム 2025/10/12)
現代では、副業が推奨され、フリーランス保護法の制定など、会社に縛られない自由な働き方に注目が集まっています。そのような中で、この判決は、副業やフリーランスとして働くときに、陥りがちな落とし穴の存在を示しています。
日常語の「労働者」と法律上の「労働者」の意味の違い
実は、この裁判の意味を理解するためには「労働者性」という言葉の理解が不可欠です。まず、私たちが会話や日常で使う「労働者」と法律上の「労働者」という用語の違いを押さえておきましょう。
多くの人は「労働」という言葉を、単純に「働くこと」「仕事に従事すること」と捉えています。アルバイトも自営業も、会社員も、家事やボランティアも、「何らかの活動を通じて価値や対価を得ること」と広く理解されているでしょう。そこから、「働く人=労働者」ととらえるのが一般的な用語です。
一方、労働基準法など労働関係法規でいう「労働者」は、「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と厳密に定義されます。
たとえば、筆者は社労士として働いていますが、個人事業主で誰にも雇われていないので、法律的な意味での「労働者」ではありません。週に2回だけの学生アルバイトは、雇われて仕事をしているのですから、法律的には「労働者」です。
そして、法律上の労働者に該当するかどうかを「労働者性」という言葉で表します。
法律上の「労働者性」が認められると、労働基準法や労災保険法、最低賃金法、社会保険、労働組合法など手厚い保護の対象となります。逆に認められないと、全て自己責任でリスクを負うことになります。
この「労働者性」があるかどうかという判断は、契約書のタイトルや肩書きでは決まらず、実態で見ます。たとえば、契約書に業務委託契約とあっても、発注者の指揮命令下で、仕事の内容や働き方が詳細に管理されていれば、「労働者」とみなされる場合があるのです。
業務委託と雇用――どこがどう違うの?
河合塾講師の事例では、名目上は「業務委託」契約。しかし、授業の時間、内容、進め方、校舎への割り振り、休憩や報告などについて学校側から明確な指示・管理を受けていました。
その結果、「実態として労働者性がある」と認定され、契約解除=雇止めは不当だと判断されました。
働く人にとって「業務委託」や「請負」と、「雇用」契約の違いは、とても分かりづらいものです。その違いを具体的な事例で見ていきましょう。
請負契約の例
例えば、「自宅の壁に書棚を作ってほしい」と地元の大工さんに頼む場合。依頼主は大工さんに”成果物”である、作り付けの書棚の完成を依頼するだけで、作業内容や方法、時間配分などは全て大工さんの裁量。手伝いのスタッフを使うかどうかも任せられ、事故があった場合も発注主の責任は原則ありません。報酬は、事前に大工さんが提出した見積書を依頼主が承諾すればその金額で決まり、働いた時間単位ではありません。
雇用契約の例
一方で、会社が大工さんを社員として雇い、毎朝決まった時間に現場入りし、会社指示の仕事をする場合を考えましょう。作業内容や休憩、報告方法まで会社の管理指示に従い、給料は時給や月給制で支払われます。怪我や病気の場合は労災・健康保険や休業補償制度もあり、書棚を作り付けるという依頼主への責任は、原則会社側にあります。
どちらもやっている作業は「個人宅で作り付けの書棚を作成・設置する」という同じ内容です。しかし、請負契約だと労働者としての保護はなにもなく、雇用契約で指揮命令に従って働いている場合とは、明確に区別されています。
フリーランスや副業に広がる偽装請負の現実
人件費や社会保険料負担を抑えるために、本来は雇用契約であるのに、「業務委託」「個人事業主」として契約を切り替える企業側の動きは、ここ20年ほどの間に加速しています。
IT、制作、教育、流通、多くの業種で行われていますが、名目上は業務委託であっても、報酬は時給換算、業務・時間・場所まで詳細に指示され、1社依存で実質的に会社の都合で働いている方はとても多いのです。
実際に、このような事例がよく見られます。
- 「Web制作業務委託だが、週5日フルタイム常駐、タスクも全部会社側社員から指示されている」
- 「教育現場で、シフトも管理も指導も学校側で決めているため個人事業主なのに自由がない」
- 「飲食チェーンの店長業務を委託契約で受けているが、売上・シフトも本部指示。休みも自分で決められない」
このような「業務委託」の募集は、類似の仕事より多少時給がよい場合も多いのですが、そこにひっかかってはいけません。会社からすれば、雇用・労災保険もかける必要がなく、社会保険の会社負担分もありません。残業代も必要ありません。また、有期契約をくりかえした場合、無期契約に転換する必要もなく、都合が悪くなればいつでも契約解除できます。会社にとってのメリットばかりで、「偽装請負」で雇われる人にとっては、なんのメリットもありません。
実態は、法的な「労働者」なのに、“名ばかり個人事業主”として、最低賃金・残業代・社会保険・労災などの保護を受けられない危険な契約です。
副業・フリーランスの保護が社会の課題に
一方、近年ではフリーランス保護の機運が高まっています。
2024年11月には、フリーランス保護法が施行されました。また、いままで建設業の一人親方等に限られていた労災の特別加入も、一定条件のもと、フリーランスも対象として認められるようになりました。例えばIT・教育・運送分野でも、条件を満たせば自分の責任で労災に加入でき、仕事中の事故・病気の補償や医療費の給付が受けられるようになっています。
ただし、これはあくまでも、本来のフリーランスへの保護が手厚くなったということであり、実態が「労働者性」を満たせば、発注先=実質雇用主へ請求や救済を求めるのが本来の姿です。
契約前に考えるべき事――その仕事は本当にフリーランスとしての自由があるか?
では、働きたい内容の仕事が「業務委託」として募集されていたら、どのように考えたらよいのでしょうか。
次の内容を頭において、今後の副業、フリーランスとしての仕事のやり方を見直してみましょう。
- 契約だけでなく、働き方の実態をチェックする
次の内容でほんとうの業務委託なのか、実態は雇用なのかチェックしましょう。
・指揮命令/時間管理/業務指示があるか
・仕事を断る自由があるか、代替性があるか(他の人を代わりに入れてもよいか)
・報酬が労務・時間の対価か成果物か
・1社に縛られ「命令に逆らえない」状態か - 複数の発注先、営業・交渉力を持つ
フリーランスの最大の武器は「仕事を選べる・増やせる」こと。1社依存なら自由どころか、その会社の出す条件を飲まざるを得ず、労働者としての保護もないという困ったことになります。 - リスクや悩みは遠慮せず相談を
契約の実態に疑問、不安があれば、労働基準監督署やフリーランス向けの相談窓口等の行政の窓口や業界団体に早めに相談し、自分の権利や安全を守ってください。
おわりに――働き方の本質を問い直す
河合塾講師事件は、契約書のタイトルや会社側の説明だけでなく、実際にどんな働き方をしているかで自身の立場・権利・保護が決まるという、現代人にとって非常に大切な教訓を示してくれました。
副業・フリーランスの世界が広がるほど、そのリスクや落とし穴も身近になってきます。
自由と不安定は、紙一重。だからこそ契約や働き方の本当の意味をよく知り、自分の価値ある人生と仕事を守ってください。