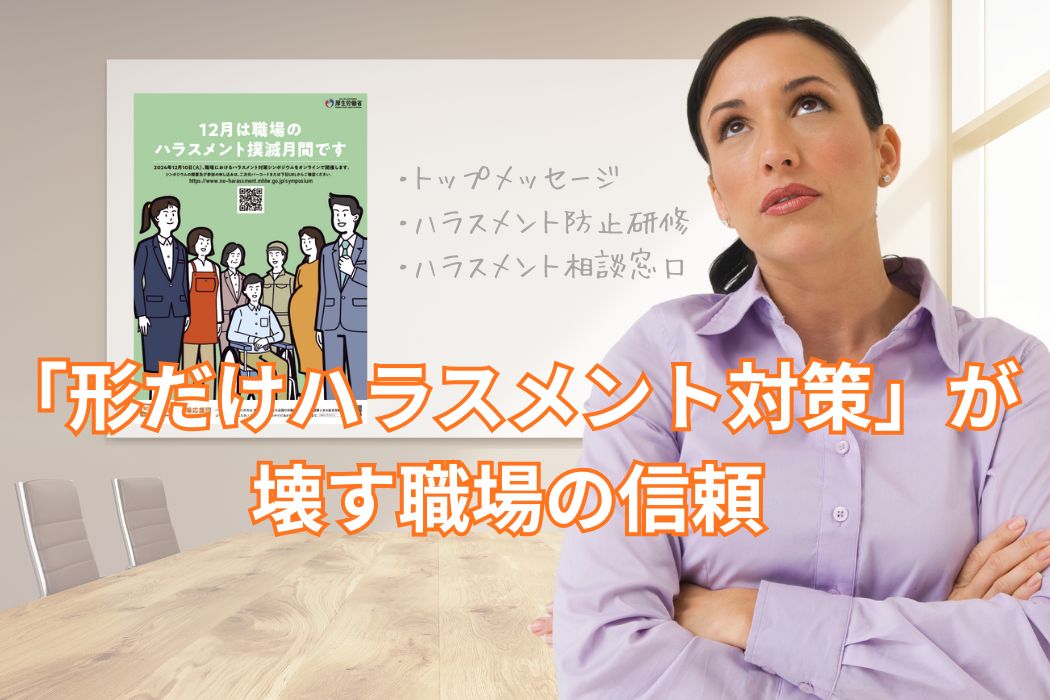ハラスメント対策は職場環境の改善に欠かせない取り組みです。
しかし、会社がハラスメント対策に熱心に取り組めば取り組むほど、社内から反発や不満が生じるケースがあります。
人事部等の担当部署からすると「がんばっているのに、だれも協力してくれない」「文句ばかり言われる」と意気阻喪してしまうこともあるでしょう。
また、必要な業務指導までもがハラスメント扱いされる事態や、管理職が適切な指導を躊躇するようになるケース、日常的なコミュニケーションへの過敏反応など、対策の過度な厳格化が新たな問題を生むこともあります。
このような事態を防ぐには、単に「何がNGか」を示すだけでなく、「どうすればよいか」という具体的な行動指針が必要です。
そこで注目したいのが「ナッジ」の活用です。
ナッジとは「選択の自由を奪ったり歪めたりすることなく、ささやかなキッカケによって自発的な行動変容を促すこと」と定義され、強制ではなく自然と望ましい選択をしたくなる環境を整えるアプローチです。
本記事では、このナッジの考え方を活用したハラスメント予防の具体的な方法をご紹介します。
ナッジとは:行動を促す「そっと後押し」
ナッジは英語で「軽く肘で突く」という意味で、強制ではなく、自発的な行動変容を促す仕組みを指します。
例えば、コロナ禍でよく見られた「ソーシャルディスタンスを確保するために床に一定間隔で靴底のイラストをプリントする」という施策は典型的なナッジです。
「ここに立ってください」と指示するのではなく、自然と適切な距離を保てるよう環境をデザインしています。
「ナッジ vs ハラスメント」という観点で考えると、両者の決定的な違いは、選択の自由にあります。
ナッジは選択肢を複数提示し、冷静な判断のもとで選べる環境をつくり出す「そっと後押し」する手法です。
一方、ハラスメントは相手の選択の自由を奪う強制的な行為といえるでしょう。
例えば、ある会社で「締切を守れない人は始末書」というルールを導入したケースを考えてみましょう。
これは強制であり、無理な締切を設定している場合などはパワハラとみなされる可能性さえあります。
しかし、ある会社では「締切の1週間前に『ここまでできました』と進捗を共有し合う15分のティータイム」を設けたところ、誰も強制されていないのに自然と準備が進むようになったといいます。
これが典型的なナッジの事例です。
EASTフレームワークで考えるハラスメント予防
ナッジを設計する際には、EAST(Easy, Attractive, Social, Timely)というフレームワークが効果的です。
これを活用してハラスメント予防のナッジを考えてみましょう。
1. Easy(簡単)
人は簡単にできることを選ぶ傾向があります。ハラスメント予防に関しても、望ましい行動を取りやすくする工夫が必要です。
具体的なナッジ例:
- ハラスメント相談窓口へのアクセス方法を簡素化する
- わかりやすい言葉で書かれたハラスメント防止ガイドラインを作成する
- 「相手を尊重する簡潔な伝え方」のテンプレートを提供する
日本語には「手取り足取り」「至れり尽くせり」という言い方があります。
そんなふうに思ってもらえるよう、考えてみましょう。
2. Attractive(魅力的)
人は魅力を感じるものに惹かれます。
ハラスメント予防の取り組みも、参加する価値や魅力を感じられるものにしましょう。
具体的なナッジ例:
- 良好なコミュニケーションを行った社員を表彰する制度の導入
- ハラスメント防止研修を参加型のワークショップ形式にして魅力を高める
- 「サンクスカード」のような肯定的フィードバックツールの導入
企業での実例として、コミュニケーションを高めるためのサンクスカードや業績をたたえるための表彰制度は、Attractiveの要素を含むナッジと言えます。
3. Social(社会性)
人は他者の行動に強く影響を受けます。
周囲の人がどのように行動しているかという社会的証明(他者がどのように行動しているかを示し、それを基に自分も同じように行動するよう促す手法)を活用することで、望ましい行動を促進できます。
具体的なナッジ例:
- 「当社の95%の社員がハラスメント防止研修に参加しています」といった社会的証明の活用
- 尊重し合うコミュニケーションの好事例を社内報で共有する
- チーム内での定期的な相互フィードバックの仕組みづくり
このほか、職場での「境内理論」の活用も効果的です。
神社の境内に入ると自然と静かになるように、特定の場(例:研修室や会議室)では自然と丁寧なコミュニケーションが生まれる環境づくりをするのです。
4. Timely(適時性)
人には行動変容を受け入れやすいタイミングがあります。
適切なタイミングでナッジを提供することで効果が高まります。
具体的なナッジ例:
- 新入社員研修や昇進時など、役割変化のタイミングでのハラスメント防止教育
- ストレスが高まりやすい繁忙期前に、コミュニケーションの注意点をリマインドする
- ハラスメント事例が報道された際に、自社の取り組みを振り返る機会を設ける
悪いナッジ(スラッジ)に注意する
ナッジを導入する際には、「スラッジ」と呼ばれる悪いナッジに注意する必要があります。
スラッジとは消費者(職場では従業員)の便益を損ねてしまうナッジのことです。
たとえば、サービスや会員資格の解約手続きを意図的に複雑にして、ユーザーが諦めてしまうように設計する仕組み(例:解約ページを見つけにくくする、解約理由を何度も聞き返す、電話でしか解約できないようにするなど)は典型的なスラッジです。
避けるべきスラッジの例:
- 特定の個人を公の場で晒すような実績の掲示
- 「やる気のある社員とない社員の差が一目でわかるよう、実績を廊下に貼り出す」といった施策
- 「今月の業績目標未達成の社員は、全員土曜日に研修です」といった強制的な取り組み
これらは一見ナッジを装っていますが、実質的には選択の自由を奪い、場合によってはハラスメントになりかねない施策です。
真のナッジは人々の選択の自由を尊重しながら、より良い選択を自発的にしやすくする環境を整えるものであることを忘れないようにしましょう。
ハラスメント予防のためのナッジ導入ステップ
ハラスメント予防にナッジを活用するための具体的なステップを以下にまとめます。
- 現状分析: 職場で起こりやすいハラスメントのパターンや原因を把握する
- ターゲット行動の特定: どのような行動変容が必要かを明確にする
- EASTフレームワークに基づくナッジの設計: 上記4つの観点からナッジを設計する
- 小規模な試行と効果測定: まずは小さな範囲で試し、効果を測定する
- 改善と拡大: 効果があったナッジを改善し、組織全体に展開する
結論:自発的な行動変容を促す環境づくり
ハラスメント予防は、単なる罰則や強制ではなく、望ましい行動を自然と選びたくなる環境づくりが重要です。
ナッジとは、人間の無意識のバイアスや性質を利用し、アメやムチに過度に依存しない手法です。
ナッジの考え方を活用することで、「こうしなければならない」という義務感ではなく、「自然とこうしたくなる」という内発的な動機づけを促すことができます。
社内研修などでも、「ハラスメントをしたら罰則がある」という脅しではなく、「相手を尊重するコミュニケーションがもたらす職場の良い変化」を具体的に示す方が効果的でしょう。
職場のハラスメント問題は複雑な課題ですが、ナッジという新しいアプローチを取り入れることで、より効果的かつ持続可能な予防策を実現できるのではないでしょうか。
この記事を自組織の状況に合わせてカスタマイズし、よりよい職場環境づくりに役立てましょう。
「うちの会社ではどのようにしたらいいのかな?」とお思いの場合は、ぜひメンタルサポートろうむにご相談ください。