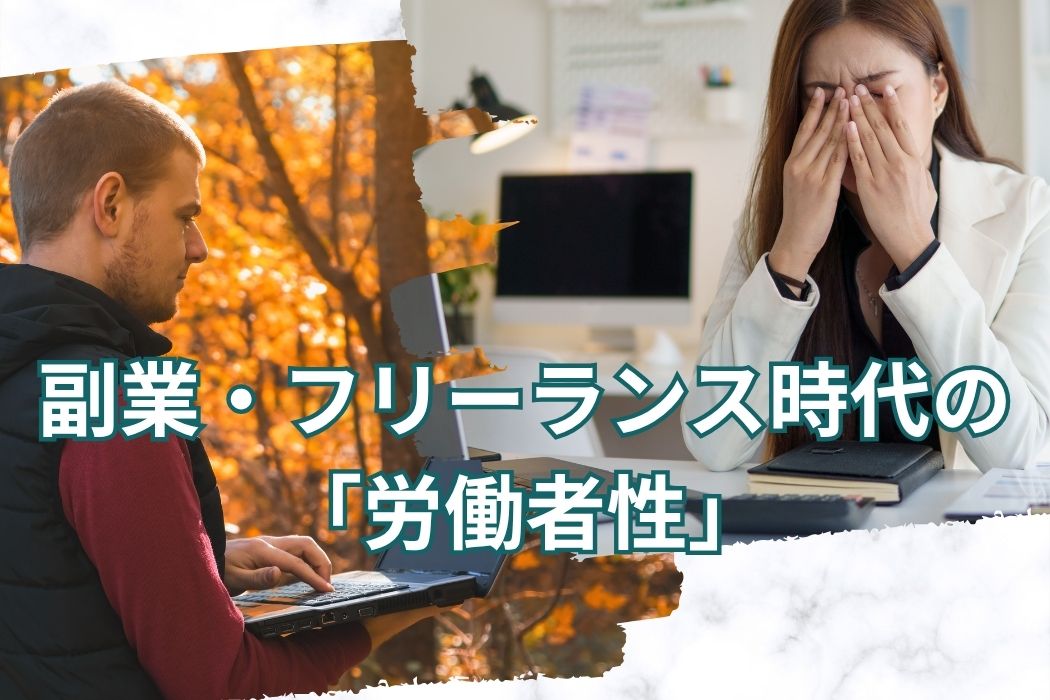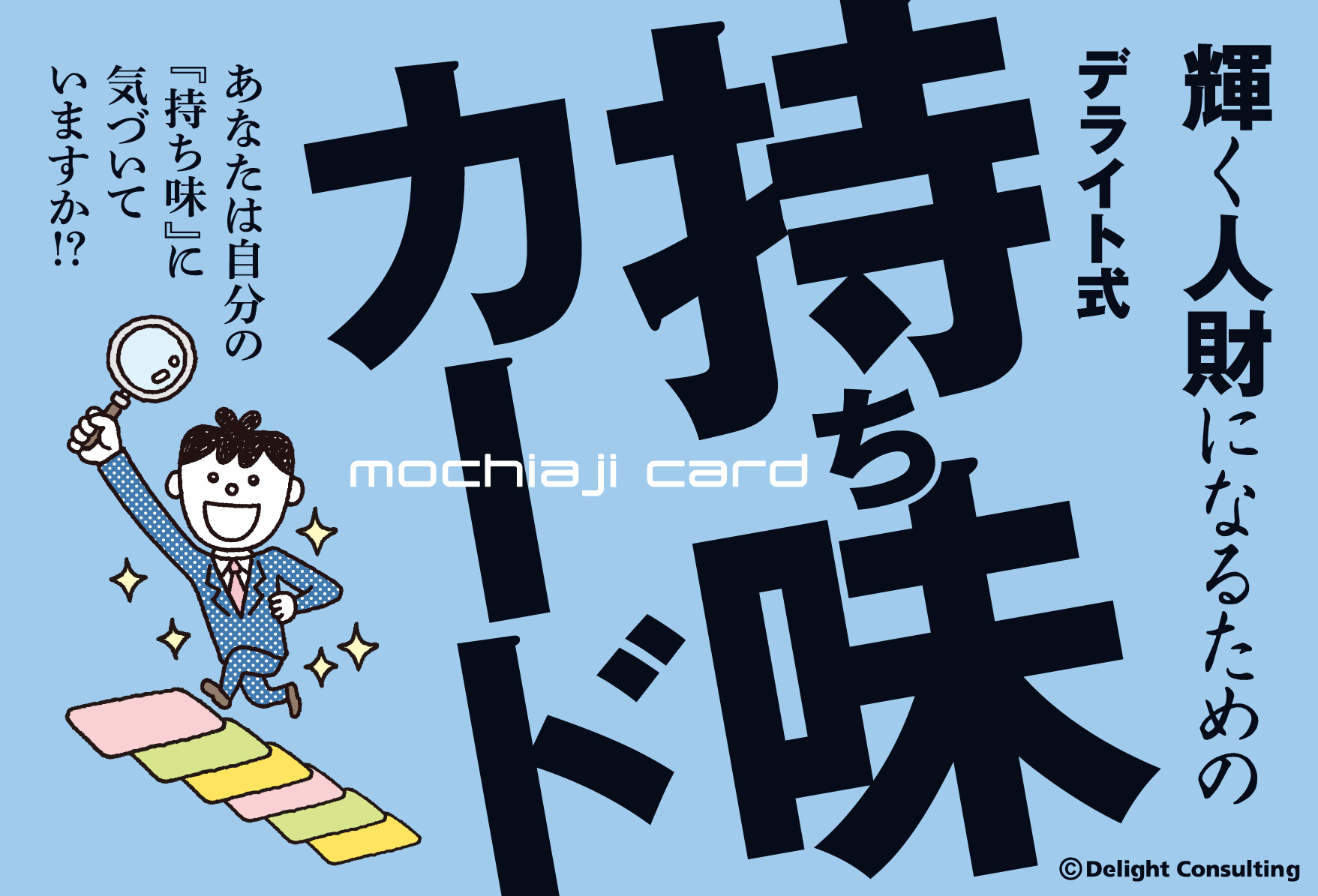「新卒で入社して10年勤めた社員が能力不足を理由に解雇され、その解雇が東京地裁で有効とされた」というニュースが、最近報じられました。(能力不足解雇が有効に 新卒入社10年目で 東京地裁|労働新聞 ニュース|労働新聞社 )
会社はこの社員が入社後10年近くの間、何度も部署を替えたり、個別に指導したり、なんとか育てようと努力しました。しかし、どうしても求められる仕事水準に届かず、本人にも改善の兆しがまったくないという状態でした。裁判所はこの状況から、「会社はできる限りのことをやった」と判断し、解雇を認めたわけです。
会社が期待する能力がない以上、解雇されてもしかたがない。当然の判決だ。このように思った人もいるでしょう。
一方、労働関係の裁判にくわしい人であれば、「めったにない判決だ」と感じたのではないでしょうか。日本の裁判では、能力不足の解雇で会社が勝訴することは難しいのです。
しかし、この判決は、これからは能力不足でクビにできる時代になったということではありません。基本的には解雇は難しく、この判決は例外的に解雇できる条件があったと見るべきです。
この記事では、能力不足解雇は実際どれだけ難しいのか、その例外の条件、会社としての備え、同僚に能力不足社員がいたらどうしたらよいか、ということを、社会保険労務士としてわかりやすく解説します。
能力不足解雇が裁判で認められるのは超難関
日本の解雇ルール(労働契約法16条)は、客観的で合理的理由があり、社会的に見て妥当な場合しか解雇を認めません。
とくに能力不足が原因の場合は、本人の努力や成長可能性を慎重に見極める必要があり、とにかくハードルが高いのです。
裁判で解雇が認められない典型パターンは次のようなものです。
- 「ちょっと頑張りが足りない」「前より成績が悪い」
- 評価が曖昧、指導が口頭でちょっと指摘しただけ
- 会社がすぐに戦力外扱いして、異動も研修もろくにしなかった
「使えないと思ったらクビにできる」という簡単な話ではまったくありません。
裁判で例外的に認められた事例のポイント
難しいとはいっても、冒頭のニュースのように、能力不足の解雇がぜったいにムリなわけではありません。最近の判決から、どのような場合に、例外的に解雇が有効となったのかを紹介します。
中途採用の即戦力が求められていた場合
あるメーカーが、専門技術を期待して中途採用。しかし現場で何度もミス、再教育も再配置もしたが、本人はマニュアルも読まず、指示されたことも繰り返し失敗。
社内の配置転換記録、指導経過、品質データ全部を出して「ここまでやっても改善しなかった」と証明し、解雇が認められました。
(Zemax Japan事件:東京地裁令和3年7月8日判決)
管理職としての適格性が極めて欠如していた場合
ある企業で、部門長クラスの管理職が任命されたものの、「部下指導がまったくできず、職場の混乱を長期的にもたらした」「組織的マネジメント能力が著しく不足」と判断された事例です。
会社は、役職降格や他部署への異動指導など、段階的措置を繰り返しましたが、状況悪化が続いたため、最終的に管理者としての信頼を大きく損なったことが記録により認定され、解雇が有効と判断されました。
(幕内国際システム事件:東京地裁平成28年3月31日判決)
事例C:高度専門職であるのに基準未達が明確だった場合
大手メーカーで、高度な技術や資格を前提としたスペシャリスト社員が採用されたケース。その社員は期待された研究成果や特許出願、現場サポートに著しく達しなかったうえ、複数回のスキル研修と上司の個別指導にも成果が出ませんでした。「基準が明示的に定められていた」こと、「社外でも同等資格者なら通常達成できる内容だった」ことなど、客観的根拠が出され、解雇有効となりました。
(コインベスト事件:東京地裁令和4年7月11日判決など)
3つの判決に共通するポイントは、「さまざまな方法を尽くしている」、「能力不足と判断した根拠の明確さ」ということです。
会社はどう動くべきか-実務で押さえたいポイント
「能力不足の社員がいて困った……」そんな時、紹介した判決のポイントをふまえて、会社がとるべき対策は次のようなものです。
- 教育・指導・面談の記録を地道に残す
- 評価や目標はなるべく“数値化”する
- 部署移動やOJT、外部研修などを複数試みる
- 評価シートをつけることを本人にも伝え、内容も定期的に共有する
- 改善計画書や本人の自己評価(振り返り)も文書にして残す
こうして、会社はできるだけのことをした、改善余地がなかったということを客観的に積み上げていくことが何より大切です。
同僚として「能力不足」の社員とどう向き合うか
実際に、自分の職場にどうしても仕事がうまくできていない仲間がいると、「またか……」「なぜ自分ばかりフォローを?」とイライラしたり、時には業務負担がふくらみストレスを感じることもあるでしょう。ですが、そんなときこそ、自身のストレスを減らし、チーム全体の成長につなげるために、次のような方法をおすすめします。
相手を“悪者”と決めつけず、まず事実ベースで
感情的に「できない人」「困った人」とラベリングするのではなく、「どんな作業でどんな困難が生じているのか」事実ベースで状況を整理しましょう。
もし“なぜできないのか”を客観的に観察できれば、本人の強みや苦手への気づきから新しい役割分担など改善策が見えてくることも。
フォローに限界や疑問を持ったら、1人で抱え込まない
つい我慢して自分が全部引き受けてしまう人も多いですが、無理を続けると心身ともに疲れてしまいます。直属の上司や人事担当に「今こういうサポート状況」「業務負担の偏り」など具体的に共有することで、職場全体でどう支えるか検討するきっかけになります。
チームとしての支える体制・伝える工夫
本人の気持ちや誇りを傷つけないよう、直球の否定や陰口はできるだけ避けましょう。
小さな成功の共有や具体的な手順化、周囲の協力体制づくりも、チームでの成果のために大切な考え方です。
本人自身の成長や希望も尊重
「なぜ続けているのか」「本当はどんな仕事をしてみたいのか」……意外に、本人が声に出せていない変化や希望がある場合も。本音を聴く場づくりやカジュアルな対話も、チームの一員として大切な働きかけです。
能力不足の問題は決して個人が全て悪いのではなく、「評価・育成・配置・チーム運営」のすべてが関わっています。困難な状況や負担感を感じる時、一人で抱え込まず、組織全体の課題として向き合っていくことが健全な人間関係や働きやすい職場づくりへの第一歩なのです。
人を育てる記録こそが会社のリスクヘッジ
能力不足による解雇は、会社側の根気も覚悟も必要です。しかし、本気で悩み抜いて対応したことは、ちゃんと積み重ねれば組織の成長力の担保や労務リスク軽減にもつながります。
「うちはここまでサポートした!」と自信をもって言える体制づくりが、いざという時に会社も社員も守ってくれるセーフティネットになるはずです。
皆さんの会社では、評価やサポート、記録の仕組みは整っていますか?
気になったら、自分の部署からだけでも、今日からでも始めてみてください。