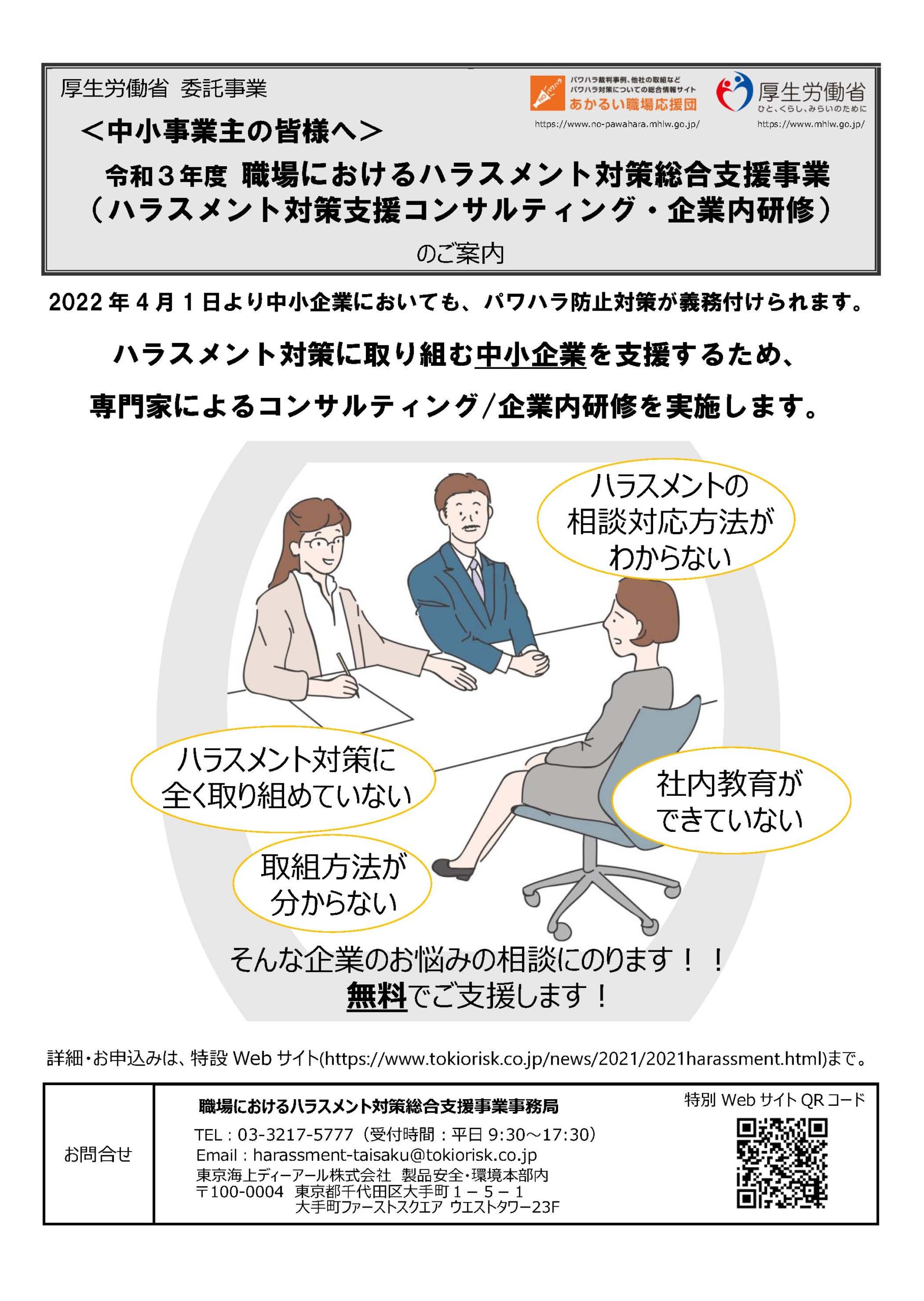(2025年5月20日追記)このブログでとりあげたXのポストについて、NHKの見解は次のとおりです。
5月15日に番組公式Xに掲載したオックスフォードに関する記述について、正確さ・丁寧さに欠ける表現がありました。ご批判ご意見を頂いており、掲載を取りやめました。お詫びいたします。
世界ふれあい街歩き – NHK
問題の所在をあえてぼかした「お詫び」ですね。下記のブログの趣旨にはとくに影響ないようですので、そのまま掲載します。画像の次の段落からが、もとの記事です。
今回はSNSで話題になった「イギリス人が多い…」という発言をきっかけに、職場で起こり得るレイシャルハラスメントやアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)、そしてダイバーシティ(多様性)の大切さについて、日本の職場の現実に即して考察します。
NHK公式アカウントの発言に感じた残念さ
まず、この話題となった発言について簡単にご紹介します。
NHKの公式X(旧Twitter)アカウントが、次のように投稿しました。
【#イギリス オックスフォード 街歩き情報② ちょっぴり裏話】 ▼・ᴥ・▼移民が多く暮らすロンドンと比べて、イギリス人が多い。昔ながらのイギリスが味わえる街です。 ↓↓↓ 街を歩いてみて・ディレクター談
私はこの投稿を読んだとき、とても残念な気持ちになりました。これは海外ロケを日常的に行っているプロデューサーによる発言です。グローバルな現場を知るはずのプロフェッショナルでさえ、無意識のうちに見た目や出身で人を分類してしまう現実を痛感したからです。
NHKは日本を代表するメディア企業であり、その発信力や社会的影響力は計り知れません。そうした立場の公式発言が、無意識の偏見やレイシャルハラスメントにつながりかねない内容であったことは、私たちにとって大きな警鐘だと感じます。
「イギリス人が多い…」発言の何が問題なのか?
この発言は、一見すると現地の印象を素直に述べているだけのようにも思えます。しかし、実際には「イギリス人」と「外国人」を見た目や先入観で区別してしまう無意識の偏見(アンコンシャスバイアス)が表れています。
現代のイギリス社会は、ロンドンもオックスフォードも多様な人種・国籍の人々が暮らしており、白人である外国人、黒人であるイギリス国民というケースは珍しくありません。「イギリス人が多い」という言葉には、「白人=イギリス人」「有色人種=外国人」といった誤ったイメージや線引きを助長してしまう危険性があります。
このような発言は、特定の人種や出自を「外部者」とみなしたり、優劣をつけたりする意識を無意識のうちに助長してしまいます。特に多様性を尊重するべき現代社会においては、こうした言葉が差別や排除の温床となりかねません。
日本の職場でも起こり得る「見えない線引き」
「イギリスの話だから自分には関係ない」と感じる方もいるかもしれません。しかし、実は日本の職場でも似たような無意識の偏見やレイシャルハラスメントが日常的に起こっています。
例1:「日本語が上手ですね」と外国出身の同僚に声をかける
外国出身の従業員が流暢な日本語を話していると、つい「日本語が上手ですね」と声をかけてしまうことは多いでしょう。一見、褒め言葉のようですが、相手によっては「自分は日本人ではない」という線引きを感じさせてしまうことがあります。特に長く日本で暮らしている方や、日本で生まれ育った方にとっては、「いつまでも“外の人”扱いされている」と感じることもあるのです。
例2:「やっぱり日本人は〇〇だよね」と無意識に言ってしまう
社内の雑談で「やっぱり日本人は礼儀正しいよね」など、良い意味で使ったつもりでも、職場に多様なバックグラウンドを持つ方がいる場合、疎外感を与えてしまうことがあります。「日本人」「外国人」といったラベル分け自体が、知らず知らずのうちに壁を作ってしまうこともあるのです。
例3:外国出身の従業員に補助的な仕事ばかりを任せる
無意識のうちに「外国人だから」「日本語が母語ではないから」といった理由で、外国出身の従業員にサポート業務や補助的な仕事ばかりを割り当ててしまうケースもあります。本人の能力や意欲を正当に評価せず、チャンスを奪ってしまうのは、明らかに不当な行為です。
レイシャルハラスメントとアンコンシャスバイアスの本質
レイシャルハラスメント(レイハラ)は、人種や国籍などを理由に差別的な扱いをしたり、侮辱的な発言をしたりする行為です。本人に悪気がなくても、無意識の思い込みやステレオタイプ(固定観念)が背景にあることが多いのが特徴です。
アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)は、誰もが持っている「気づかない思い込み」であり、例えば「外国人は日本のビジネスマナーを知らないだろう」「女性はリーダーに向かない」といった考えが知らず知らずのうちに行動や判断に影響を与えます。
こうしたバイアスやハラスメントが職場に蔓延すると、外国出身の社員だけではなく、女性、高齢者、セクシュアルマイノリティ、障害者、持病のある人、育児・介護をしている人等の従業員が本来の力を発揮できなくなります。多様性を活かす組織づくりのためには、まず自分自身の無意識の偏見に気づくことが重要です。
ダイバーシティ推進のメリットと現状
多様な人材が活躍できる職場は、イノベーションや問題解決力の向上、グローバル対応力の強化など多くのメリットがあります。例えば、異なる視点や経験を持つ人材が集まることで、新しいアイデアが生まれやすくなり、変化の激しい時代にも柔軟に対応できる組織になります。
それ以前に、すでに外国出身の従業員がいないと成り立たない職場は多いでしょう。いつまでも「外の人」扱いでは、企業の業績にも影響があります。
日本企業ではまだ「同質性」が重視されがちで、外国人や女性、年齢や障がいの有無など違いを持つ人が活躍しづらい場面も少なくありません。ダイバーシティ推進は、単なる「多様な人材の採用」だけでなく、誰もが安心して自分らしく働ける環境づくりが不可欠です。
企業が取り組むべき具体策
では、こうした発言や無意識の偏見を防ぐために、会社としてどんな取り組みが必要なのでしょうか?私が現場でよく提案しているポイントをまとめます。
1. 就業規則の整備と周知
- レイシャルハラスメントや差別的言動を明確に禁止する規定を設け、全社員に周知する。
- 外国人従業員だけでなく、すべての従業員が安心して働けるルールを整備する。
2. 継続的な研修・教育
- レイシャルハラスメントやアンコンシャスバイアスに関する研修を定期的に実施する。
- 研修は一度きりで終わらず、繰り返し行うことで意識の定着を図る。
- 具体的な事例やロールプレイを取り入れ、実践的な気づきを促す。
3. 相談窓口・ホットラインの設置
- ハラスメントの相談窓口を社内外に設け、誰でも安心して相談できる体制をつくる。
- 匿名相談や多言語対応も検討し、多様な従業員が利用しやすい仕組みにする。
4. 経営層・管理職の率先垂範
- 経営層や管理職が多様性を尊重する姿勢を明確に示し、日々のコミュニケーションでも実践する。
- 「ダイバーシティ&インクルージョンは経営戦略の一部」というメッセージを発信し続ける。
5. 定期的な実態把握と改善
- 社内アンケートやヒアリングで、ハラスメントや多様性に関する課題を定期的に把握する。
- 結果をもとに施策を見直し、必要な追加対策を講じる。
まとめ:小さな気づきから職場を変える
NHKのような大企業であっても、そして海外経験豊富なプロフェッショナルであっても、無意識の偏見からは完全に自由ではいられません。
だからこそ、私たち一人ひとりが、無意識の偏見や「見た目」「出身」で人を判断しない意識を持つことが、ダイバーシティ推進の第一歩となるのです。
会社としても、ルール整備・教育・相談体制・経営層のリーダーシップを通じて、誰もが安心して力を発揮できる職場づくりを目指しましょう。
日々の小さな気づきと行動が、多様性を活かす組織文化の土台となります。