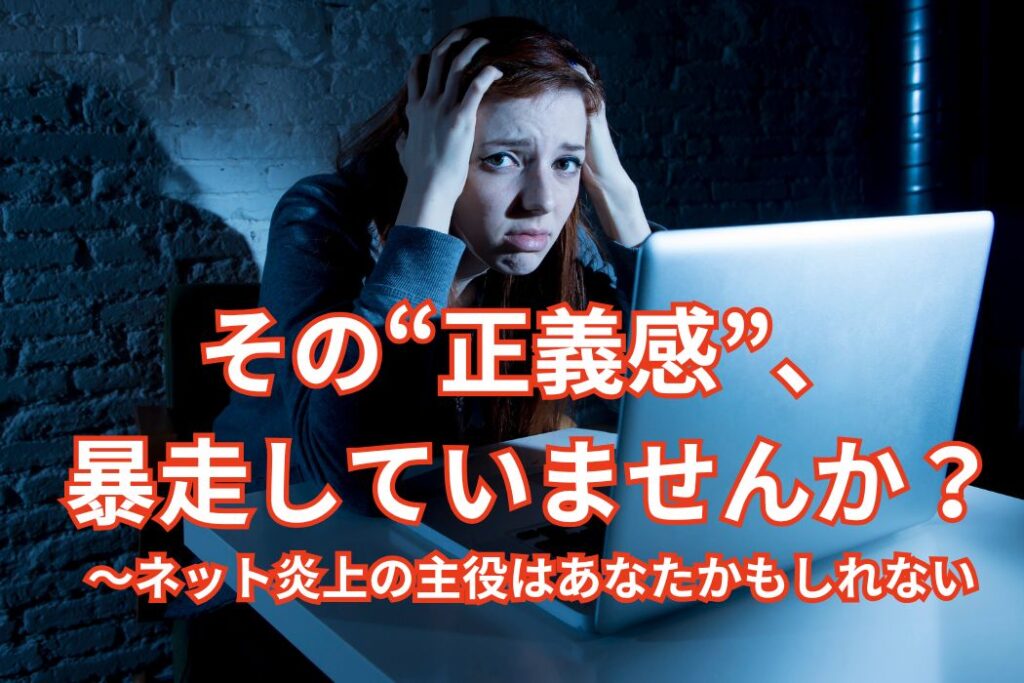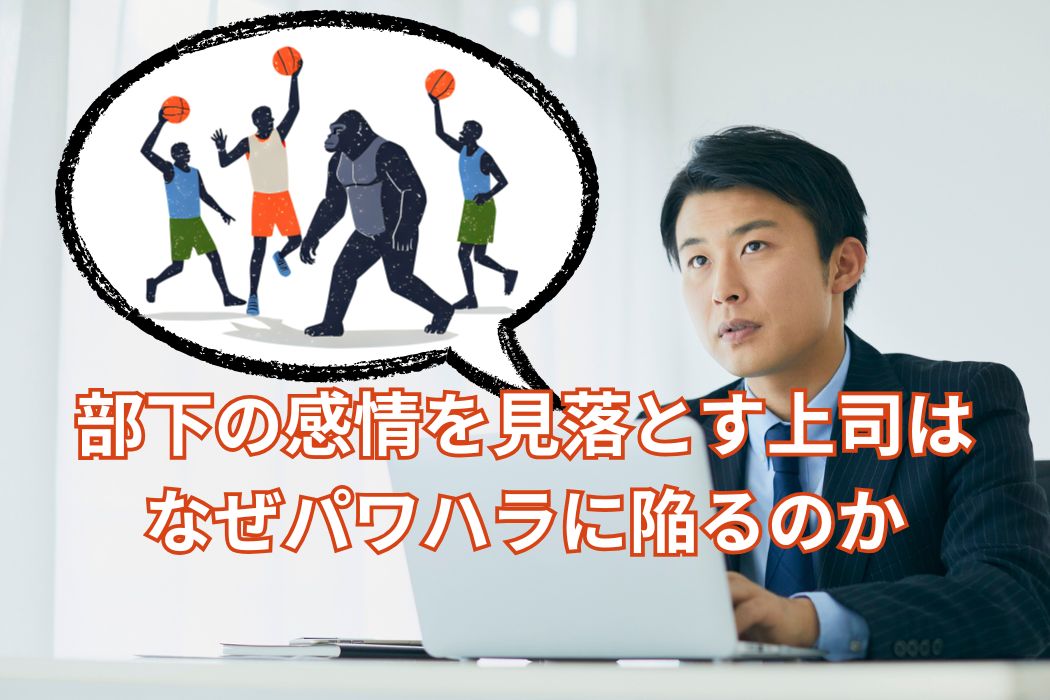ある朝、自宅近くのゴミ集積場にゴミを出しに行きました。すでに出されたゴミ袋の中に、数十個のつぶれたピンポン玉や紙くずが混ざっています。向かいの卓球場から出されたものだとすぐに気づきました。たとえ少量でも、「ここは家庭ごみ専用の場所なのに、なぜ事業ごみが?」と、ささやかな違和感が胸に残りました。
直接迷惑を被っているわけでもないのに、このモヤッとした感情が湧くのはなぜでしょうか。
公正性や共感から生まれる「代理的な正義感」
こうした感情の根底には、人が公正でありたい、というごく自然な心理があります。ルールを守る人と守らない人がいたとき、たとえ被害が自分に及ばなくても、不公平ではないかと感じるのです。この時、「本来迷惑するのは清掃職員のはず」と理解しつつも、「ルール違反はおかしい」という思いが自分の中で強調されます。
心理学的にこれは共感による反応でもあります。他者が困っていることや不正義が行われていることに対して、まるで自分ごとのように憤りや不快感を覚える。これをここでは「代理的な正義感」と呼びます。自分の正義感で、誰かのために怒る・注意するという気持ちです。
いきすぎた正義感が社会にもたらすもの
この「代理的な正義感」は、コミュニティを健全に保つ基盤でもあります。「ルールは守って当然」「違反している人を見て見ぬふりはできない」という意識があるからこそ、みんなが暮らしやすい社会になる。実際、誰も気にしなければ小さなルール違反は累積し、やがて大きな無秩序に繋がります。
一方で、この感覚が暴走したとき、社会に悪影響を及ぼすこともあります。昨今、ネット社会ではその典型例が炎上です。
ネット炎上の構図 ― 「善意」から始まる集団的攻撃
SNSやネット掲示板で、不正やマナー違反、疑惑の行動が発覚すると、多くの人が憤りの声を上げます。その多くは正義感からの行動です。「間違いを正したい」「被害者を守りたい」「社会の秩序を保ちたい」という意図そのものは、決して悪ではありません。
しかし、ネット社会においては、その正義感が増幅され、エスカレートします。知人でも当事者でもない人までが、「これは許せない」と怒り、シェアやコメントなどで攻撃が雪だるま式に広がっていきます。面識のない他人を寄ってたかって糾弾するという現象、いわゆるネットリンチが発生するのです。
その過程で、誤情報や憶測が独り歩きし、無関係な人や家族、関係ない企業にまで攻撃が及ぶことも少なくありません。
正義感が暴走するとき ―「個人の正義」は正しいのか
ネット炎上事例を分析した調査によれば、炎上や中傷に参加する人の多くは、「自分は正しいことをしている」と信じているそうです。つまり、自分なりの正義感に基づき、行動しているということです。
この「自分なりの正義」は、しばしば独善的になり、異なる価値観を持つ他者を許せなくさせます。他人を叱りつけたり、罰しようとすることで、自分の不安から解放されたり、ある種の満足感さえ得てしまうといわれます。それが加速すると、多数の人が無自覚に集団的な“いじめ”や“吊るし上げ”に加担してしまうのです。
実生活にも潜む「いきすぎた代理的な正義感」
ネット上だけではありません。職場や小さなコミュニティでも、ルール違反を糾弾することは必要ですが、方法を誤ると監視社会や息苦しさを招く場合もあります。たとえば、ささいなミスを大げさにみんなの前で批判したり、「許せない」という立場から攻撃的な言動を取ってしまう。それは本当に組織のためなのか、それとも自分の欲求の発散やストレス解消になっていないか、一度立ち止まって考えたいところです。
建設的な正義感の使い方 ~違和感を力に変えるために
違和感や正義感を感じたとき、それ自体は大切なアンテナです。しかし、その感情をどのように行動へつなげるかによって、周囲への影響や結果は大きく変わります。健全で建設的な正義感の使い方について、具体的に掘り下げてみましょう。
1. 事実確認を怠らない
まず大切なのは、「本当に問題があるのか?」という冷静な事実確認です。ネットや噂話から得た情報だけで判断してしまうと、誤解や早合点に基づく不当な批判に発展する恐れがあります。できれば複数の視点から客観的に状況を把握し、直接関係者に確認できる場合は丁寧にヒアリングするのも良いでしょう。焦らず、事実と解釈を切り分ける姿勢が大切です。
2. 伝え方・向き合い方を工夫する
何かを指摘したり注意を促したくなったとき、感情的な言葉や断定的な口調は相手を傷つけたり、防衛的にさせてしまうことがあります。「どうしてこの行動を選んだのか教えてくれる?」など、相手の事情や背景にも関心を示しつつ建設的な対話を心がけましょう。また、「みんなで良くしたい」、「自分も学びたい」というスタンスで臨むことで、相手との信頼関係も深まります。批判よりも提案や対話を重視する姿勢が、長期的には問題解決につながります。
3. 感情の棚卸しをする
自分が感じている怒りや苛立ちの正体を、冷静に見つめ直すことも欠かせません。「自分は何に対してどんな気持ちを持っているのか」「なぜ、こんなに強く反応してしまうのか」を内省し、必要であれば紙に書き出して整理してみると良いでしょう。単なる自己満足やストレスのはけ口になっていないかをチェックし、本当に守りたい価値や目的を明確化します。
4. 「みんなのため」のつもりが誰かを傷つけていないか振り返る
正義感に基づいた行動が、知らず知らずのうちに誰かを一方的に攻撃したり孤立させたりしていないか、常に振り返ることも大事です。「正論」や「ルール遵守」を楯に過剰な非難をしていないかどうか、自身のコミュニケーションスタイルも定期的に見直しましょう。また、個人攻撃ではなく、「システムやルール自体の改善提案」に視点をずらしてみるのも有効です。
5. ポジティブな影響を広げる
気づいた問題点を指摘するだけでなく、「こうすればもっと良くなる」「こんな工夫ができる」といった前向きなアイディアや行動を提案することで、周囲の人も自然と前向きに参加できる雰囲気を生み出します。正義感を“誰かを罰する”ためでなく、“みんなが安心して過ごせる場づくり”のために活用する。それが組織や社会全体の成長につながります。
正義感は、適切な方法で使えば、職場でも地域でも大切な連帯や改善の原動力となります。感情に引っぱられず、相手に配慮し、未来志向の対話を意識することで、より良いコミュニティやチームづくりに確実につなげることができます。
健全なコミュニティづくりのために
ゴミ捨て場で感じたささやかな違和感をきっかけに、「正義感」について考えてみました。社会や組織の健全性を保つためには、適切な正義感がとても大切です。しかし、暴走した「代理的な正義感」は、ネット炎上のように誰かを不要に傷付け、混乱を広げてしまうリスクも孕んでいます。
個人の中の「正義」と、他者の権利や尊厳、社会全体のバランス。それぞれを意識しながら、まずは思いやりと冷静さを大切に、健全なコミュニティづくりを皆で目指したいものです。