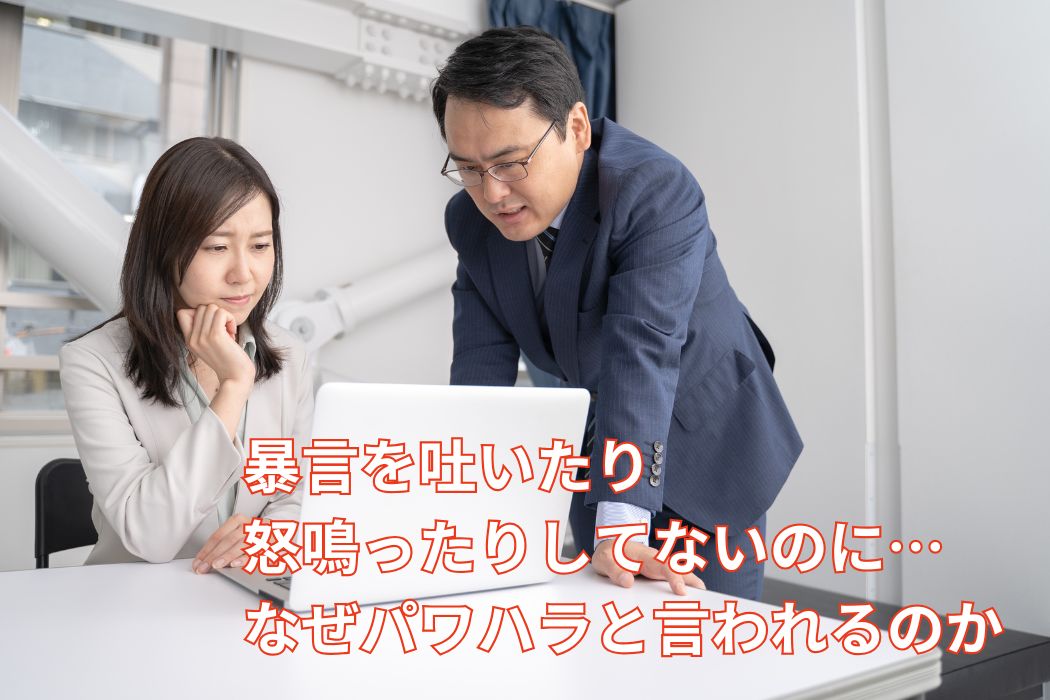最近、外食店を訪れた際に目にする光景が変わってきています。席につくとまず目に飛び込んでくるのはタッチパネル式の注文端末、料理を運んでくるのは配膳ロボット、そして会計は自動精算機で済ませる──。便利になった、いや人間に対応してもらいたい、ロボットがかわいい⋯利用者の側からはさまざまな感想が出てきますが、実はこれらの光景は、外食産業における深刻な人手不足を象徴するものなのです 。
実際に、外食産業の43.8%が「慢性的な人手不足」に直面しており、配膳業務においても35.2%が人員不足による効率低下を課題としています。(【飲食店における配膳業務の課題と自動化ニーズに関する調査】 キングソフト株式会社 )自動化の波は、単なる効率化ではなく、人手が足りない現実への切実な対応策なのです。
この記事では、外食産業で店長が長時間労働に陥りやすい構造的な背景とその法的な側面、そして外食産業で働く労働者がどのように自分を守るべきかを、社労士の視点から解説します。
店長の3割が過労死ラインを超え、労災も増加
2025年10月28日、厚生労働省が公表した「過労死等防止対策白書(2025年版)」により、外食産業の深刻な労働実態が改めて浮き彫りになりました 。この調査では、外食産業で働く1,200人を対象に労働時間を調査し、店長などの店舗責任者の約3割が過労死ライン(週60時間以上)で働いているという衝撃的な結果が明らかになったのです。
具体的には、店長の29.0%、エリアマネジャーやスーパーバイザーの24.0%が過去1カ月のうち平均的な1週間で60時間以上働いていることが判明しました 。週60時間の労働は月の残業時間に換算すると約80時間に相当し、これは過労死の労災認定基準となる時間に達します 。
さらに深刻なのは、この長時間労働が実際に労災の増加につながっていることです。飲食・運輸業では「残業80時間」を超える労働者が18%に上り、これらの業種で精神障害による労災認定件数が増加傾向にあることが白書で明らかになっています 。
時間外労働の法的規制と36協定の基本
このような外食産業での深刻な長時間労働は、法律上の規制を満たしているのでしょうか。
労働基準法では、使用者は原則として1日8時間、週40時間を超えて労働者を働かせることができません 。これを超えて従業員を労働させる場合は、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の締結と労働基準監督署への届け出が必要になります 。
2019年4月から施行された働き方改革関連法により、時間外労働には罰則付きの上限規制が設けられました 。36協定を締結した場合でも、原則として時間外労働の上限は月45時間、年360時間までとされています 。
特別条項付き36協定を締結した場合であっても、以下の上限を超えることはできません。
- 年720時間以内
- 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
- 月100時間未満(休日労働を含む)
- 月45時間を超える月は年6回まで
法定労働時間を超えた場合、使用者は25%割り増しした残業代を支払う必要があります 。深夜労働(22時〜5時)には追加で25%、法定休日労働には35%の割増賃金が必要です。
過労死白書で明らかになったような、恒常的に残業が80時間を超えている労働者の存在する事業所では、労働時間の上限規制が守られておらず違法状態であることが強く疑われます。
なぜ外食産業で長時間労働がなくならないのか
(1)少子高齢化と業界特有の人手不足問題
外食産業の人手不足は単なる一時的な現象ではありません。日本の生産年齢人口の減少により、これまで店舗運営を支えていた若年層のアルバイトの数が圧倒的に減少しています 。
さらに外食産業は全業種中最も高い離職率(年間26.6%)を記録しており、アルバイトでは31.9%に達します 。
この背景には、立ち仕事中心の体力的負担、深夜・24時間営業への対応、クレーム対応などの精神的ストレス、そして価格競争による処遇改善の困難という業界特有の構造的問題があります 。これらの複合的要因により、店長などの管理職に業務が集中する構造が根深く存在しているのです 。
(2)低価格競争が生む管理監督者へのしわ寄せ
同じ外食店で働く店長以外の従業員の状況を見ると、接客担当従業員は6.0%、調理担当従業員は13.3%しか週60時間以上働いておらず、店長だけが突出して長時間労働に陥っている状況が浮かび上がります 。
店長に負担が集中する状況の原因は、このように考えられます。
外食産業では激しい価格競争が続いており、人件費の抑制が経営の重要課題となっています。人手不足だからといって給与を上げることはできず、客離れを恐れて値上げも難しい。この中で、多くの経営者が「店長は管理監督者だから残業代を支払わなくても法律に触れない」「長時間働かせても問題ない」という誤った認識を持っているケースが見られます。
労働基準法上の管理監督者は単に役職名が「店長」や「マネージャー」であることを意味するものではありません。法律上の管理監督者に該当するためには、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間等の規制になじまず、その地位にふさわしい待遇がなされている必要があります 。
この認識の誤りにより、本来は一般労働者として保護されるべき店長が、違法な長時間労働を強いられるという問題が生まれています。低価格競争の中でコストカットの「調整弁」として店長が利用され、過労死ラインを超える労働を余儀なくされているのが実情です。
(3)店長が管理監督者に該当するかどうか争われた日本マクドナルド事件
外食産業の店長が管理監督者に該当するかどうかについては、重要な判例があります。
日本マクドナルド事件(東京地判2008年1月28日)では、マクドナルドの店長が管理監督者に該当するかが争われ、裁判所は以下の理由で店長が管理監督者ではないと判断しました。
- 店舗の営業時間や営業方針は本社が決定し、店長の裁量は限定的
- アルバイトの採用権限はあるが、人事考課は本社が実施
- 管理職手当は支給されているが、長時間労働により時間単価は一般従業員を下回る場合がある
- 遅刻・早退時には減給処分を受ける可能性があり、労働時間の規制を受けている
この判決により、外食産業の店長であっても、実態として管理監督者の要件を満たさない場合は、適切な労働時間管理と割増賃金の支払いが必要であることが明確になりました。
しかしその後も、多くの店舗で「管理監督者」の名のもとに、残業代も労働時間規制もない店長たちが働いているのです。
外食産業で働く労働者が自分を守るには
このような中、外食産業で働く労働者が自分を守るには、どのようにしたらよいのでしょうか。
(1)労働時間の記録を残す
最も重要なことは、自分の労働時間を正確に記録することです。タイムカードだけでなく、実際の出勤・退勤時間、休憩時間の実態を日記やスマートフォンのメモ機能で記録しておくことが労災認定や未払い残業代請求において重要な証拠となります。
(2)労働組合への相談
労働組合は労働者の権利を守る組織です 。外食産業では全国規模の産業別労働組合も存在し、職場の不平・不満・悩みごとを相談できる体制が整っています。UAゼンセンなどの労働組合では、全国どこでも対応可能な相談窓口を設置しています 。
(3)行政機関への相談
労働基準監督署では労働条件に関する相談を受け付けています。また、都道府県労働局には総合労働相談コーナーが設置されており、労働問題全般について相談が可能です 。匿名での相談も可能なため、まずは情報収集から始めることをお勧めします。
(4)健康管理と早期対応
長時間労働による健康被害を防ぐため、定期的な健康チェックを欠かさず行い、体調不良や精神的な不調を感じた場合は早めに医師の診察を受けることが重要です 。外食産業ジェフ健康保険組合では、こころとからだの健康相談窓口を無料で提供しており、そのような業界特有の支援制度も活用しましょう。
業界全体で働き方改革の推進を
外食産業における長時間労働問題は、少子高齢化による労働力減少、そして業界特有の構造的問題が複合的に作用した社会問題です 。過労死白書が示すように、店長の3割が過労死ラインで働き、実際に労災も増加している現状は看過できません 。
特に問題なのは、低価格競争の中で「店長は管理監督者だから残業代不要」という誤った認識により、本来保護されるべき労働者が違法な長時間労働を強いられていることです。日本マクドナルド事件の判例が示すように、単に「店長」という役職名だけでは管理監督者には該当しません。
労働者には労働基準法をはじめとする法律によって守られる権利があり、適切な知識と対策により自分自身を守ることができます 。記録の保持、相談窓口の活用、専門家への相談など、複数の手段を組み合わせることで、健康で働きやすい職場環境の実現に向けて行動していくことが重要です。
経営者側も、法的リスクの回避と優秀な人材の確保・定着のため、適切な労働時間管理と労働環境の改善に真剣に取り組む必要があります。外食産業全体で働き方改革を推進し、持続可能な業界発展を目指すことが求められているのです 。