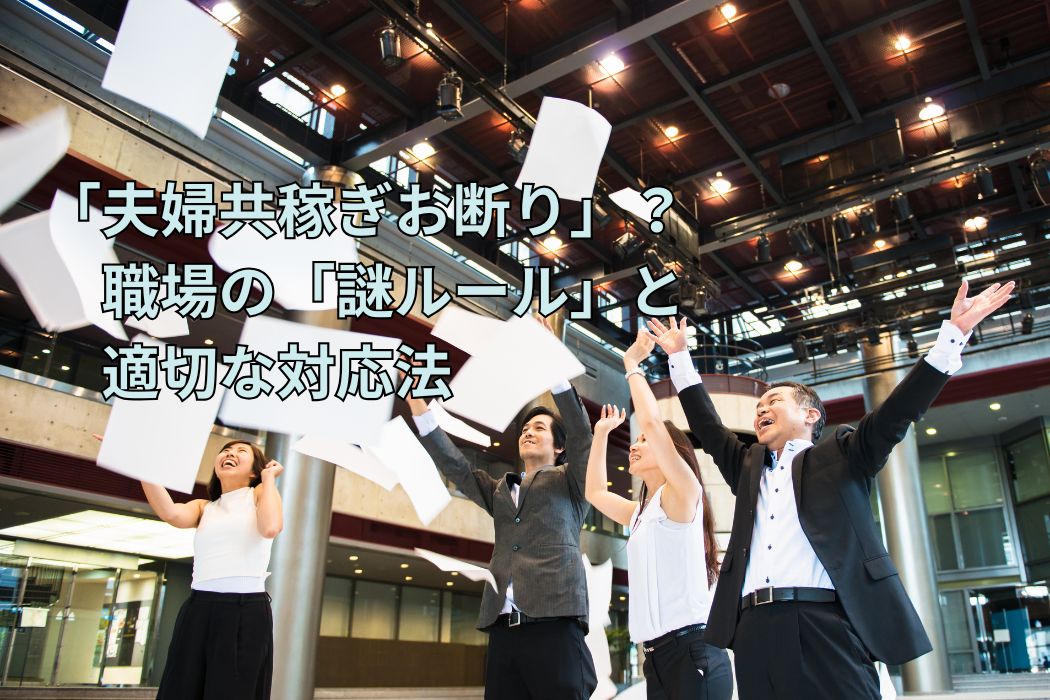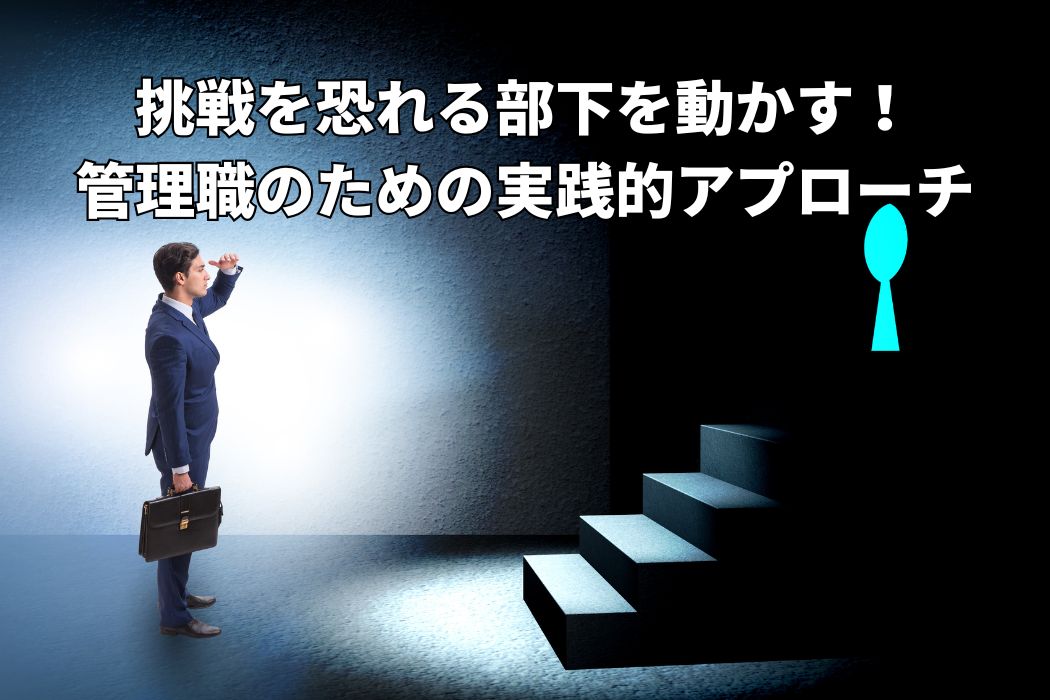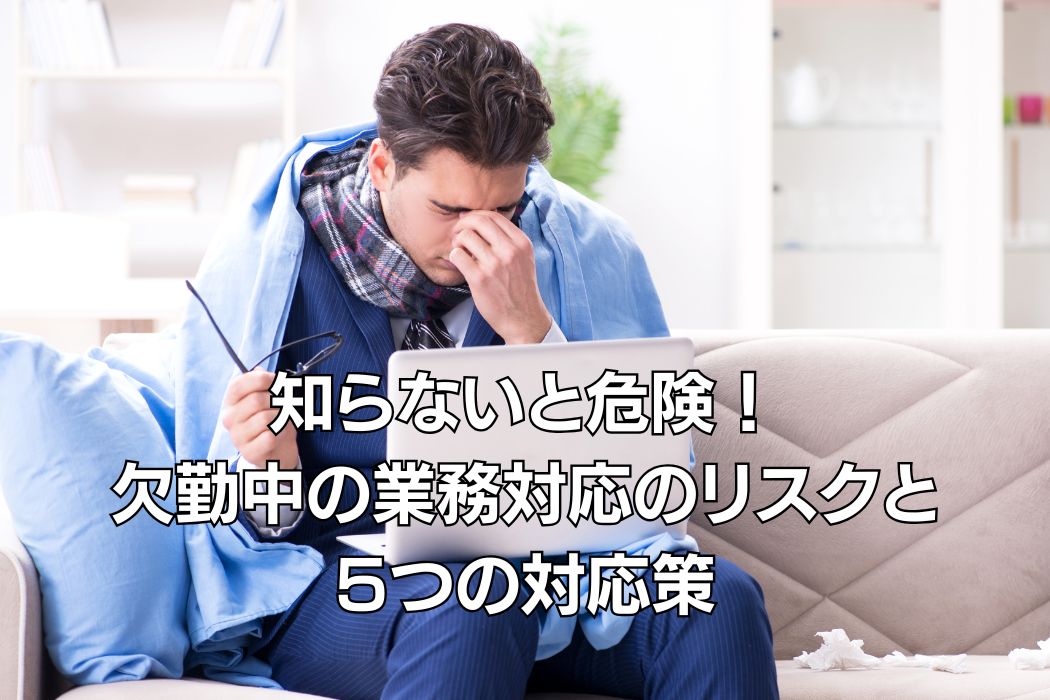「最近の若手は本当にAIを使いこなすようになったなぁ…」
会議資料を見ながら佐々木課長(48歳・入社26年目)は思いました。複雑なデータ整理も、企画書の下地作りも、AIを駆使して短時間で仕上げてくる。効率的だし、頼もしいと感じていたのです。
ところがある日、経営幹部から「この資料、どうもおかしいぞ」と指摘を受けて再チェックしたところ、AIが出したデータや文章にはいくつも誤りや抜け漏れが。若手社員は「AIで作ったから間違いないと思っていました」と言うばかり。自分の頭で考える力や、物事の本質を見抜く経験が実はほとんど積めていない⋯その事実を痛感した佐々木課長は、今の若手育成スタイルに危機感を覚えました。
AIで失われる「実感と肌感覚」
ここ1、2年で生成AIは一気に広がり、事務作業や定型的な書類作成、調査、問い合わせ対応などを驚くほど速く処理できるようになりました。プログラミング業務でさえ、以前なら初心者が行っていたような基本的なコード生成は、人間よりAIのほうが早く正確にこなしてしまう場面も増えてきています。
中堅以上の管理職にとっても、「新人がやっていた仕事はもうAIで十分では?その分、難しい業務にリソースを割こう」と、効率やコストダウン志向が強くなりがちです。
しかし、そこには大きな落とし穴が待ち構えています。
見かけ上は「AIを使いこなしている新世代」が増えていますが、実際にはAIの出力そのものに致命的な誤りや論理の飛躍が含まれていることも多々あります。とくに基礎的な資料作成、調査、データ加工などで、若手がAIを信用しすぎてミスをそのまま見逃すケースがしばしば見られます。
そして、自分で「正しいか」「妥当か」と考える経験そのものが減ることで、根本的な実務力や問題発見力が身につきにくくなっているのです。
冒頭の例はフィクションですが、このような場面がこれから多く見られることでしょう。
筆者は社会保険労務士として25年以上働き、現場でAIも使いながら業務改善に取り組んできました。
自分の専門分野――労務管理や社会保険・労働保険の制度、法改正情報など――であれば、AIが出力した内容に間違いがあればすぐに気づいて、正確な情報を調べることができます。
ですが、たとえば最新の医療情報等、まったく専門外の分野のAI出力については、見た目がもっともらしいと、「本当に正しいかどうか」は判別できません。専門外になった瞬間、AIのウソをそのまま受け取ってしまう危険性を感じています。
これと同じことが社内でも起こっているのです。業務の本質を理解する・現場の知識を持つ・自分で調べて考えるという経験値が乏しいと、AIアウトプットの精度を見極める力は、なかなか養われません。
生成AIが事務作業や定型業務を肩代わりすることで、かつて若手が現場でコツコツ体得していた「ミスに気づく感覚」「上司や同僚への確認・対話」「本質を探る力」などの訓練の場が劇的に減ってしまいます。
その結果、「自分で作ってみて初めてわかる違和感」「何に気をつけるべきか」という、仕事の基礎力が身につきにくいのです。AIによる作業の効率化が進めば進むほど、皮肉にも人が成長する機会は減っていくのです。
就職氷河期世代の苦しみ——組織と個人
ここで思い出すのは、かつての就職氷河期世代です。新卒採用の時期に多くの企業が採用を絞ったため、正規雇用の機会を失い、派遣や契約社員で働く人が他の世代より多くなっています。
企業から見ると、中堅層〜管理職の空白が長く続き、その結果、業務運営の継続性が絶たれ、今も世代間断絶や持続的成長の困難に苦しんでいる企業が多いのです。
氷河期世代自身も、望んだ職種に就けない不安定な雇用が長く続き、自己肯定感の低下や将来不安、社会的孤立といった苦しみを多く抱えています。これは単なるキャリアの問題だけでなく、社会全体の不安要素となり、少子化とも密接に関わっています。
もし今のAI時代に「実務経験を積む場」を本当に失わせてしまえば、同じような形で、新しい氷河期世代を生みだしてしまう危険があるのです。
AI時代に「人間ならではの成長」を支えるために
AIは「便利さ」「効率」「精度」「標準化」という点で大きなメリットを持ちます。ただし、人間側で「本質を探る力」「失敗を通じた学び」「現場との対話」が失われれば、組織としての強さは決して持続しません。
管理職の役割は、AIを使わせてそのまま放任することではなく、「どの工程は人間の現場経験が不可欠か」「どんな作業は人間がAI出力をダブルチェックする必要があるか」を意識的に設計していくことです。
管理職の意識だけでなく、組織としてAIを使いこなしながら、若手の人材育成をおろそかにしないためには、どのようにしたらよいのでしょうか。
次に述べるポイントを意識した組織運営を考えてみましょう。
- 若手にもあえて現場訓練と実務検証の役割を持たせる。 AIが処理した結果の妥当性チェックや、現場同行、対人調整など、人間がやるしかない仕事への経験機会を設ける。
- OJTやメンタリング体制を再構築し、「なぜこの業務はこうなったのか?」を時間をかけて伝える。 隣で議論・相談を重ねられる場を用意し、AI頼りになりすぎない空気を育てる。
- AIリテラシー研修を全社的に導入し、「ウソやハルシネーションを見抜く力」「専門外ではAIに頼りすぎない習慣」を身に付けさせる。
- 新人・若手採用や世代のバランス維持を人事戦略にきちんと組み込む。 目先の効率だけではなく、「長期の持続力」「世代継承」の視点を決して失わない。
- コミュニケーション、フィードバック、チーム対話の場を増やすよう工夫する。 機械処理では拾えない気づきや雑談を業務時間に組み込む。
AI時代だからこそ人を育てる覚悟を
生成AIは間違いなく業務の効率化をもたらし、企業の生産性と標準化を後押ししてくれます。しかし、その陰で失われていく「人間が現場で学び、問い直し、成長していく場」がどれほど重要か、今一度振り返ってみませんか。
筆者自身も、実際にAIを活用していますが、自分の専門分野ならAIの間違いをすぐに見抜けます。しかし、専門外の情報は判別が難しいという現実があり、「人がAIの精度を担保できる力」を育てることの重要性を日々痛感しています。
過去に就職氷河期世代を作ってしまった企業社会が、そのために中間層が薄く社内コミュニケーションにも困難を抱えている現実、さらに氷河期世代が抱えた「育てられなかった苦しみ」「正規雇用や社会参画から排除された痛み」を繰り返さないためにも、AIに使われるだけではなく、AIを正しく使う人を育てる。会社の経営層と管理職にはその責任があります。
“実務経験を奪うAI”の罠に陥ることなく、企業と社会の持続力を支えるために、人間が育つ現場をこれからも失わせない覚悟が、次の時代の明暗を分けるのです。