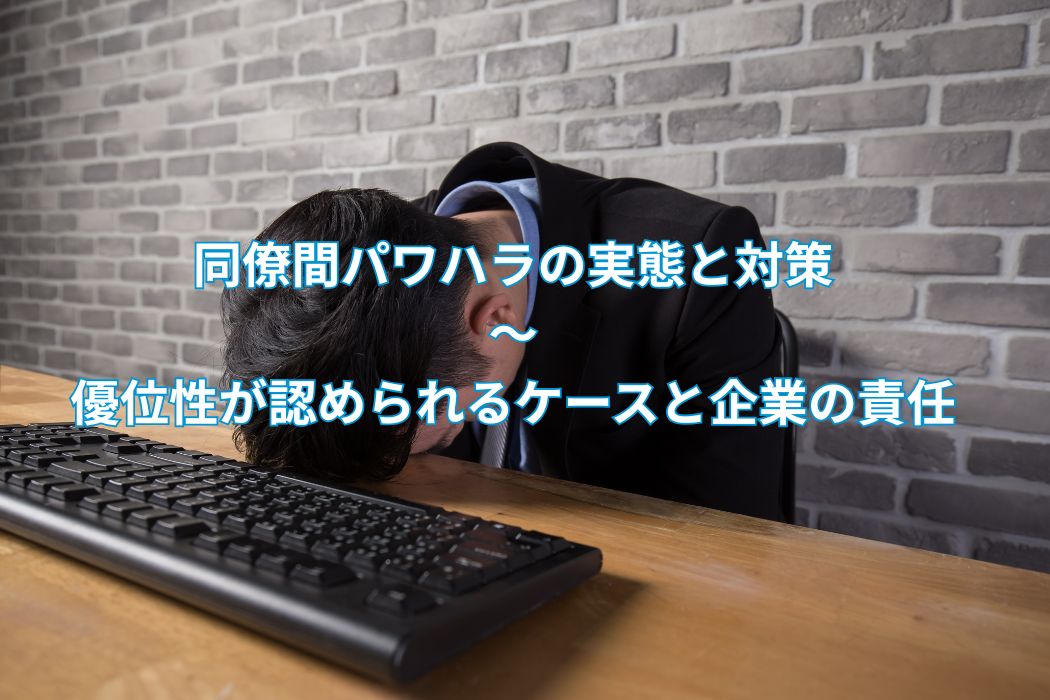「言うことを聞かないと異動させるぞ」「問題を起こして責任を取れるのか」——。
2025年9月、熊本県の阿蘇広域消防本部で、組織のトップである消防長がこうした高圧的発言を繰り返し、停職3カ月の懲戒処分を受けるというニュースが報じられました 。被害を受けた部下の中には、ストレスでうつ病を発症した職員もいたといいます 。
しかし、この事案で最も注目すべきは、2024年7月に組合職員全員を対象として実施されたハラスメントに関するアンケート調査によって問題が発覚したという点です 。消防長という組織の最高責任者からのパワハラを、誰が直接告発できるでしょうか?まさに「声なき声」を拾い上げたアンケートの威力を示す事例といえます。
この記事では、職場のハラスメント発見に効果のある、全職員アンケートの活用法を詳しく解説します。
なぜ全職員アンケートが隠れたハラスメントを暴くのか
全職員対象のアンケートは、なぜハラスメント発見に効果があるのか。ここでは3つの側面から見ていきましょう。
1.権力の壁を突き破る匿名の力
「部長から毎日のように人格否定発言を受けているが、相談したら報復されるのではないか」「課長のセクハラ発言が気になるが、証拠もないし言い出しにくい」——職場でこうした悩みを抱える従業員は決して少なくありません。
厚生労働省の調査によると、パワハラを受けた経験がある人のうち、約4割が「何もしなかった」と回答しています 。その理由として「何をしても解決にならないと思った」「職務上不利益が生じると思った」が上位を占めており、特に加害者が上司や経営層の場合、被害者が声を上げることの困難さが浮き彫りになっています。
阿蘇消防本部のケースでも、消防長という組織トップからのハラスメントを個別に相談することは、現実的に極めて困難だったでしょう。しかし、匿名性が保証されたアンケートという手法により、複数の職員が安心して実情を報告できたのです。
2.数値化される職場の「生の声」
千葉県が令和6年度に実施した職員アンケートでは、回答者8,269名のうち1,793名(21.7%)がハラスメントを受けたと感じたと回答し、そのうちパワハラが1,599名(19.3%)、セクハラが328名(4.0%)という具体的な数値が明らかになりました 。
このように、感情論や推測ではなく客観的データとして問題を可視化できることで、経営陣も「これは深刻な問題だ」と認識し、具体的な対策に乗り出すきっかけになります。「なんとなく職場の雰囲気が悪い」という曖昧な状況から、「パワハラ被害者が全体の2割を占める」という明確な課題として捉えられるようになるのです。
3.組織の本気度を示すシグナル効果
アンケート実施自体が、「会社はハラスメント防止に本気で取り組んでいる」という強力なメッセージとなります。ある外資系製造業の事例では、人事担当者が「本人は指導のつもりですが、周囲から見ればパワーハラスメント」という状況に悩んでいたところ、360度フィードバック(アンケートの一種)の導入により、「管理職の中に問題意識が芽生え、これまでの自分の言葉や行動について内省するよい機会になった」と報告しています 。
加害者側にとっては「組織が見ている」というプレッシャーが抑制効果を生み、被害者側にとっては「一人で抱え込む必要はない」という安心感を提供する効果があります。
アンケート実施時のポイント
実際にどのようにしたら、効果的なアンケートを実施することができるのでしょうか。3つのポイントをご説明します。
1.紙かWebか:現場に合わせた媒体選択
紙媒体を選ぶべきケース
- 製造現場や建設業など、ITデバイスへのアクセスが限定的な職場
- 平均年齢が高く、デジタル操作に不慣れな従業員が多い組織
- 「デジタル痕跡が残らない」という心理的安全性を重視したい場合
実際に、ある建設会社では紙のアンケートを採用した結果、現場作業員からも多数の回答を得ることができ、これまで見えていなかった現場監督とのトラブルが明らかになったという事例があります。
Web媒体を選ぶべきケース
- テレワークや複数拠点に分散している組織
- 集計・分析の効率性とコスト削減を重視する場合
- 条件分岐機能を使って詳細な情報収集を行いたい場合
IT企業の事例では、Web調査により「セクハラを受けた場合の具体的状況」「パワハラの頻度」などの詳細情報を効率的に収集し、部署別・職位別の詳細分析まで短期間で完了させることができました。
2.設問設計の具体化テクニック
悪い設問例
「職場でセクシャルハラスメントを受けたことがありますか?」
良い設問例
「以下のような言動を職場で経験したことがありますか?
- 性的な話題や冗談を聞かされた
- 身体を不必要に触られた
- 容姿について性的な評価をされた
- プライベートな異性関係について詮索された」
具体的行為例を示すことで、「これもセクハラだったのか」という気づきを促し、回答精度を大幅に向上させることができます。
3.適切なフィードバックの重要性
アンケート実施後、結果のフィードバックを怠ると従業員の不安が一気に拡大します。
「アンケートに答えたが、その後何も音沙汰がない」「もしかして自分の回答が問題視されているのか?」「会社は本当に改善する気があるのか?」といった疑念が職場に広がってしまいます。
ある製造業の事例では、ハラスメントアンケート実施後2ヶ月間何の報告もなかったため、「人事部が隠蔽している」「経営陣がもみ消しを図っている」といった憶測が飛び交い、かえって職場の雰囲気が悪化したという失敗事例があります。
集計が終了したら、数値部分だけでも従業員に公表し、記述部分について、「早急に取り組む」姿勢を明確にしましょう。
組織の「覚悟」が生む変革の力
阿蘇消防本部の事例は、組織が真摯にハラスメント問題と向き合う覚悟の重要性を教えてくれます。消防長という組織のトップが加害者であっても、職員全員アンケートで明らかになった事実に基づき、第三者委員会を設置し、適切な処分を科すという一連の対応は、決して容易な判断ではなかったはずです。
実は、アンケート実施前の段階ですら、「なにが出てくるか恐ろしい」「アンケートで出てきた問題に対処するには人手が足りない」等、しりごみする役員も珍しくありません。アンケート実施は問題に取り組む第一歩であるとともに、踏み出すには、経営陣の「覚悟」が必要なものなのです。
しかし、この「覚悟」こそが、真のハラスメント防止につながります。表面的な研修や形式的な相談窓口設置だけでは、根本的解決は望めません。組織が本気でハラスメントと戦う意志を示し、その意志を全職員アンケートという具体的行動で表現することで、初めて職場環境の本質的改善が可能になるのです。
「誰も取り残さない職場」の実現——それは経営陣の決断から始まります。全職員アンケートは、その決断を形にする最も効果的なツールの一つなのです。
現代の職場環境において、ハラスメント防止は法的義務であると同時に、優秀な人材確保と組織パフォーマンス向上の基盤でもあります。阿蘇消防本部のように、問題を隠蔽せず真正面から向き合う組織こそが、持続的成長を実現できるのです。
あなたの組織は、本当の意味でハラスメント防止に取り組む準備ができているでしょうか?
全職員アンケートは、その答えを教えてくれるはずです。