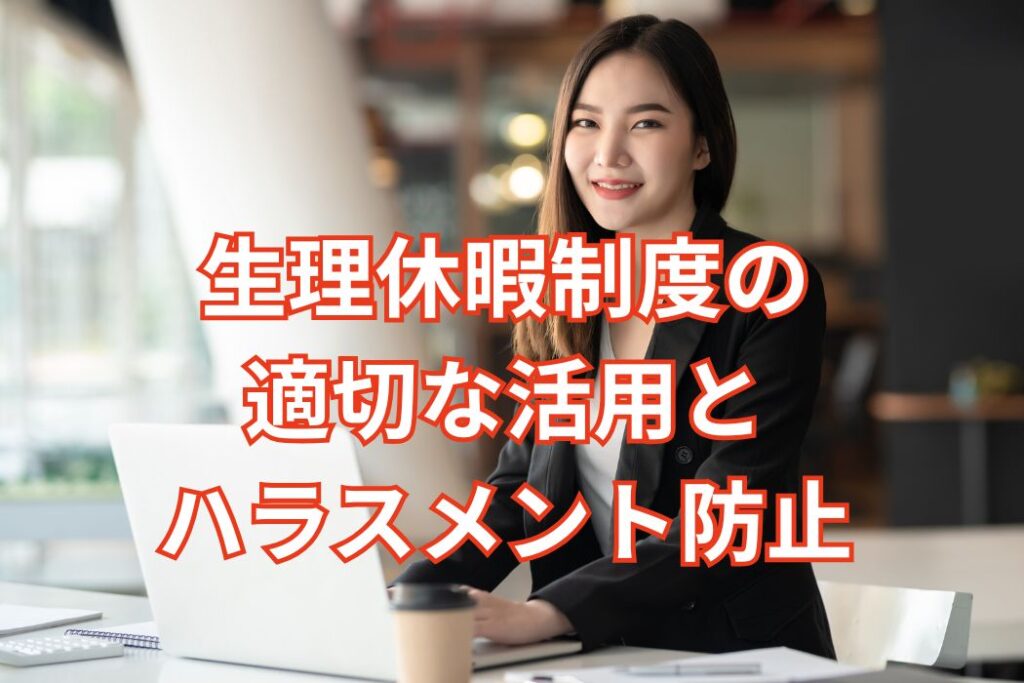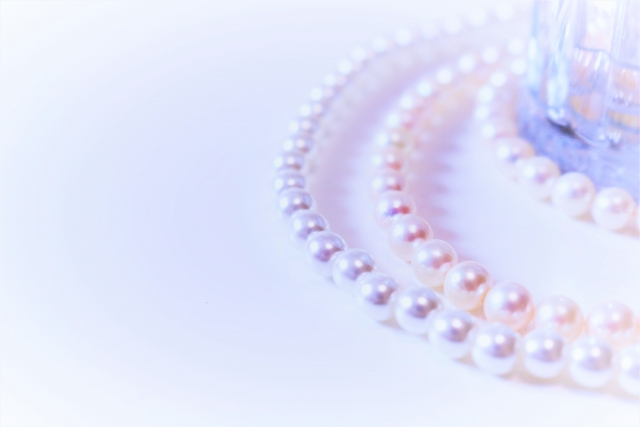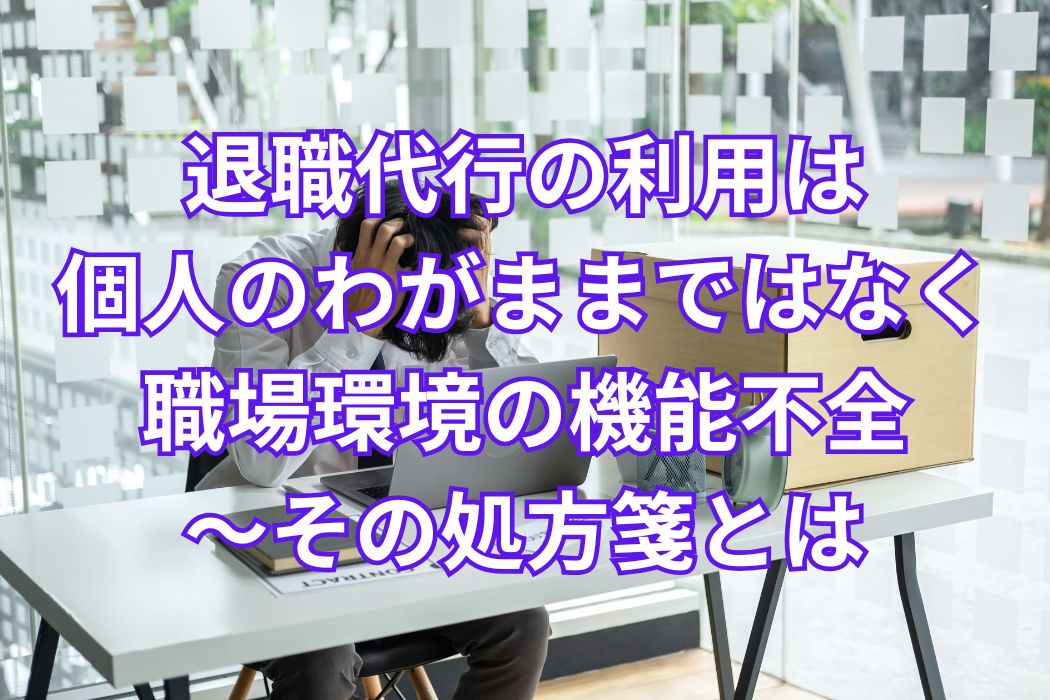生理休暇制度について、企業の人事労務担当者や管理職の方から「制度はあるが運用に困っている」「どこまで確認していいのかわからない」「ハラスメントと言われないか心配」といった相談を受けることがあります。一方で、働く女性からは「制度があっても使いにくい」「上司に言い出せない」といった声も聞かれます。
この記事では、労働基準法第68条の規定内容から職場環境の改善方法まで、生理休暇制度の正しい理解と適切な運用を目的として解説します。特に、セクハラ・パワハラとなる具体的な言動例を明示し、管理職の不安を解消しながら、女性従業員が安心して制度を利用できる環境整備の方法を提案します。
活用されていない現実
日本は1947年に世界で最初に生理休暇を法制化した国です。現在、法制化している国は韓国、台湾、インドネシア、ザンビア、スペイン(2023年)など約6か国のみで、世界的に非常に珍しい制度です。
ヨーロッパでは「性別による雇用差別の禁止原則に反する」「性差別を助長する」といった反対論もあり、慎重な議論が続いています。このような国際的背景を考えると、日本が持つこの制度は女性の働きやすさを支える貴重な仕組みといえます。
ところが、せっかく制度があっても利用されているかというと、現実はかなりお寒い状況です。
2020年に生理休暇を利用したことのある女性は0.9%。生理休暇の申し出があった事業所は3.3%。ほとんど利用されていないことが、数字からわかります。(参考:働く女性と生理休暇について/令和5年9月28日 厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課)
この低い取得率の背景には「上司に言いにくい」「周囲の目が気になる」といった職場の雰囲気があります。制度は存在するものの、実際には活用されない「絵に描いた餅」状態が続いているのです。
女性の働きやすさを真に実現するためには、制度の正しい理解と適切な職場環境の整備が不可欠です。
労働基準法第68条の基本規定
生理休暇の根拠となっているのは、労働基準法第68条です。まず、その中身を確認してみましょう。
取得対象と条件
生理休暇はすべての女性労働者が対象となります。正社員、契約社員、パート、アルバイトなど雇用形態を問わず、生理による下腹痛、腰痛、頭痛等により就業が困難な場合に請求できます。重要なのは、就業規則に記載がなくても取得可能な法定休暇であることです。
日数制限と取得単位
労働基準法では取得日数に上限がありません。企業が「月○日まで」といった制限を設けることは違法です。また、1日単位だけでなく、半日や時間単位での取得も認められており、症状の程度に応じて柔軟に対応できます。
申請方法
診断書や証明書の提出は原則として不要で、本人の申告のみで取得可能です。企業は申請を拒否できず、違反した場合は30万円以下の罰金が科せられます。
賃金の取り扱い:有給か無給か
法律上、生理休暇の賃金については企業の判断に委ねられています。有給でも無給でも違法ではありません。
出勤率算定での配慮
無給の場合でも、年次有給休暇の出勤率算定では出勤扱いにすることが推奨されています。厚生労働省も「生理休暇について、出勤率の算定に当たって出勤したものとみなすことも差し支えありません」と明記しており、女性労働者への重要な配慮措置です。
取得しやすい環境づくり
では、生理休暇を取得しやすくするには、どのような点を変えていけばよいのでしょうか。生理休暇を機能させるには、管理職の意識改革が鍵となります。しかし、意識改革だけでは不十分で、制度面・環境面・運用面での包括的な改善が必要です。
制度の名称変更で心理的ハードルを下げる
「生理休暇」という名称自体が取得を阻む要因となっています。男性社員や男性上司がいる場合、恥ずかしさや言いにくさが生じるためです。効果的な名称変更の例として「体調管理休暇」「ヘルスケア休暇」「Life Style Support休暇」などがあり、実際に取得率が大幅に改善した企業が多数報告されています。
申請手続きの簡素化
申請の心理的ハードルを下げるため、勤怠システムからのワンクリック申請、チャットツールでの簡易申請など、デジタル化を推進します。書類提出や事前申請を不要とし、当日の体調に応じた柔軟な対応を可能にすることが重要です。
教育・研修体制の構築
管理職向けには生理に関する基礎知識の提供と適切な対応方法を、全従業員向けには男性社員も含めた正しい知識の共有を行います。定期的なセミナーや社内イントラネットでの情報発信も効果的です。
相談体制と職場風土の改善
人事部への相談窓口設置、女性社員によるピアサポート体制、産業医・保健師による健康相談など、多様な相談窓口を設置します。また、経営陣からの明確なメッセージ発信により、トップダウンでの意識改革を進めることで、生理に関する話題をタブー視せず、自然に相談できる職場風土を醸成できます。
これらの取り組みを体系的に実施することで、生理休暇が真に機能する職場環境を構築できるでしょう。
ハラスメント防止:絶対に避けるべき言動
そして、多くの管理職や人事労務担当者が気にしている「生理休暇について話題にするとハラスメントになるのでは?」という疑問については、次のような点を理解しておくようにしましょう。
セクシュアルハラスメントとなる質問
下のような質問や発言はセクハラに該当する可能性が高いので避けましょう。
- 生理の周期や症状を詳しく聞くこと
- 「生理の周期から考えて今日休暇を取るのはおかしい」
- 「その歳で生理休暇を申し出るのは変だ」
- 「今日は生理日か?」と推測で聞くこと
人事院のセクハラ基準でも、体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」と言うことがセクハラの例として明記されており、発言者の意図に関係なく相手が不快に感じればセクハラとなります。
パワーハラスメントとなる行為
また、以下の言動はパワハラに該当する可能性が極めて高いものです。
- 「仕事を優先しろ」「使えない」などの否定的発言
- 「頻繁に取らないようにな!」といった威圧的発言
- 嫌な顔をする、迷惑そうな態度を示す
- 「生理休暇は査定に響く」という評価への脅し
- 実際に人事評価で不利に扱うこと(これは違法行為)
適切な対応方法と制度設計
生理休暇の申請には「お疲れさまです。お大事にしてください」程度の配慮ある対応に留め、特別な感情を表に出さず淡々と手続きを進めることが適切です。詳細を聞かず、本人の申告を尊重しましょう。
ひょっとしてこれは、ウソの申告、つまり不正取得ではないかと感じても、人権侵害せずに生理の真偽を確認することは実質的に不可能です。厚生労働省も原則として特別な証明は不要としており、本人の申告を尊重することが基本です。詳しく質問すればセクハラ、否定的態度を示せばパワハラとなるため、直接的な確認は避けるべきです。
明らかに矛盾する客観的証拠(旅行に行った、激しいスポーツをしていた等)がある場合に限り、極めて慎重な事実確認が許容される可能性がありますが、「月経期間中でも一時的な外出は可能」という主張が認められるケースもあり、立証は非常に困難です。
「ほんとうに生理なのか?」と直接尋ねるのではなく、次のように制度設計で不正利用防止することを考えましょう。
- 無給制度の採用または有給日数の上限設定
- 就業規則への懲戒処分規定の明記
- 制度の適正利用に関する周知文書の配布
制度を活かすために
生理休暇は法的権利でありながら、実際の取得率は極めて低い状況が続いています。この現状を変えるには、企業の意識改革と職場環境の整備が不可欠です。
管理職への教育徹底、ハラスメント防止策の実施、制度の適切な周知を通じて、女性が安心して申請できる職場を作ることが重要です。同時に、不正取得への懸念は制度設計による間接的な抑制で対応し、直接的な詮索は避けるべきです。
日本が世界に先駆けて導入した貴重な制度を真に機能させることで、すべての働く女性が能力を十分発揮できる社会の実現につなげていきましょう。適切な理解と運用により、生理休暇が女性の働きやすさを支える実効性のある制度として機能することを期待します。