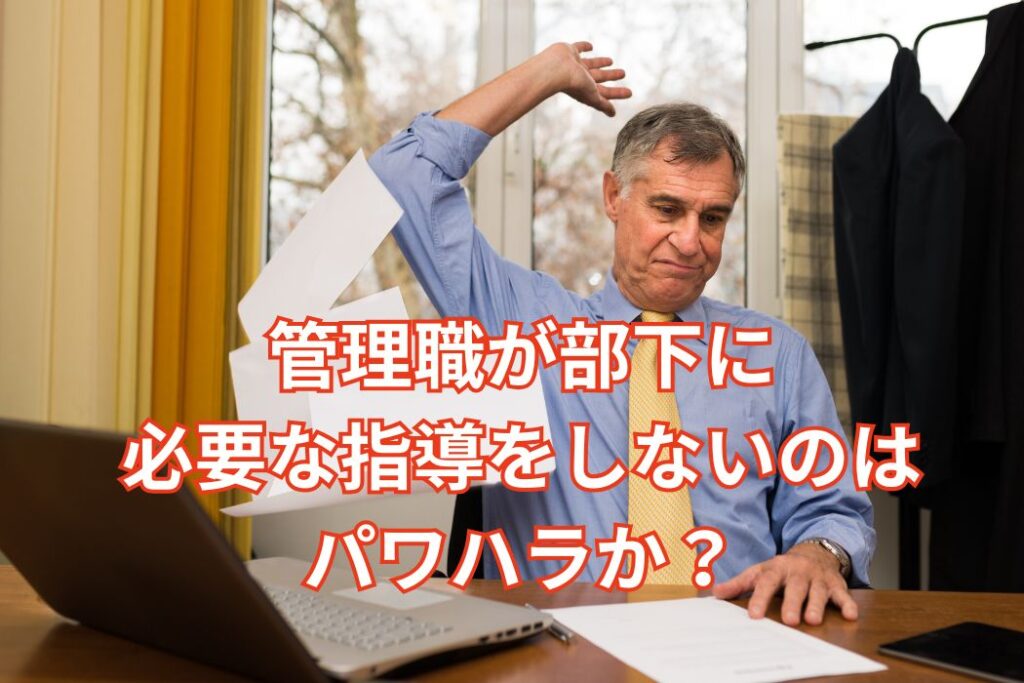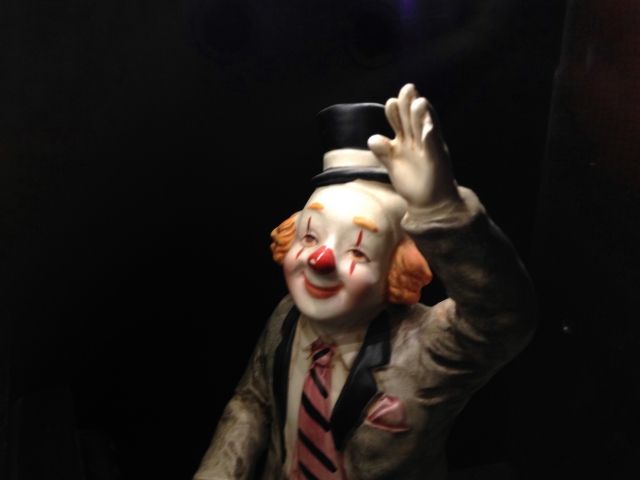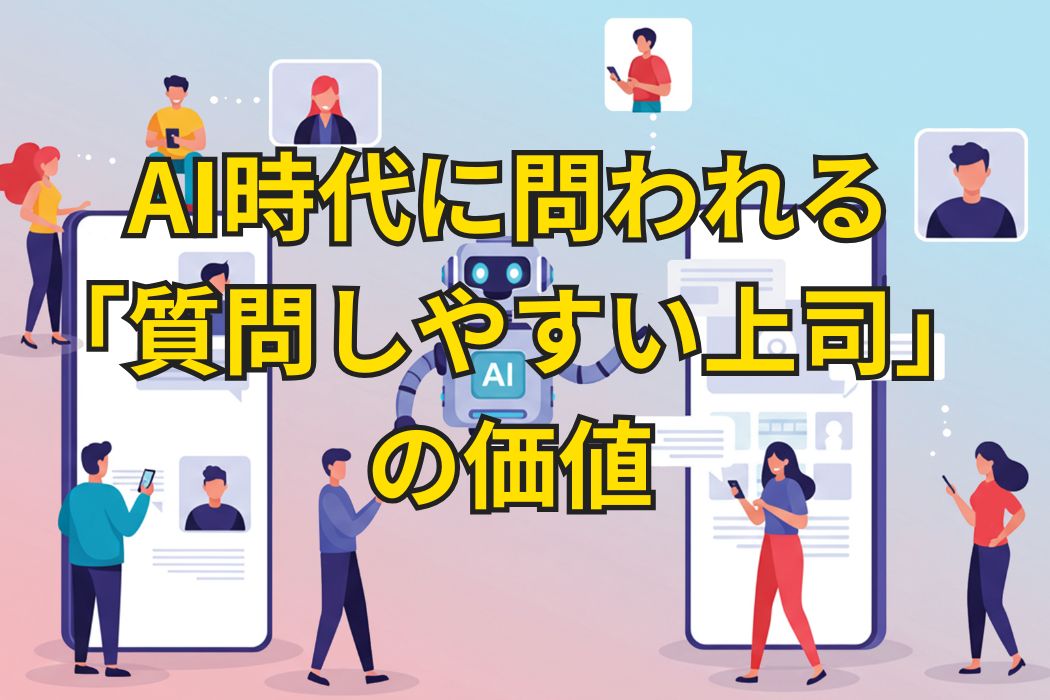このブログの最後に、わかりやすく説明した動画があります。あわせてご利用ください。
「入社して半年が経ちましたが、上司からの指示や指導はほとんどありません。何をどう進めればよいのか分からず、質問しても『自分で考えて』としか言われません。仕事がうまくいかず、毎日が苦痛です。最近は、このままでは成長できないと感じ、退職も考え始めています。」
これは、実際に多くの若手社員が感じている悩みの一例です。
上司からの適切な指導やフィードバックがなければ、部下は自分の役割や仕事の進め方に自信を持てず、孤立感や不安を深めてしまいます。こうした状況が長く続くと、心身の不調や退職につながることも珍しくありません。
管理職が指導を避ける背景――「パワハラ」と言われる不安
なぜ管理職は、部下への必要な指導やフィードバックをしないのでしょうか。その背景には、厳しく指導することでパワハラと言われることへの過剰な恐れがあると考えられます。
経団連が2021年に実施した「職場のハラスメント防止に関するアンケート結果」では、企業の現場で深刻な問題が浮き彫りになっています。調査では、「パワハラと指摘されてしまうのを恐れ、必要な範囲の厳しい指導が難しいという管理職のジレンマ」や、「上司が適切な指導に対して、萎縮する懸念。何かあると部下から『ハラスメントだ』と言われることを恐れるあまり、仕事を抱えてしまう、適切な部下指導が出来ない管理職がいる」という声が報告されています。
さらに、「指導とハラスメントの境界線が線引きしづらい」という現実的な課題も明らかになっており、管理職が必要な指導まで避けてしまう「指導萎縮症候群」が広がっていることが分かります。
パワハラの定義と3要件
では、指導とパワハラはどのように区別されるのでしょうか。
パワハラは、労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)で次のように定義されています。
「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されるもの」
この定義は、以下の3つの要件に分けて考えます。この3つすべてを満たす場合に、パワハラと認定されます。
1. 優越的な関係を背景とした言動
上司や先輩など、職場内で地位や人間関係において優位に立つ者が、その立場を背景に行う言動が該当します。管理職から部下への行為が典型ですが、同僚や部下からであっても、集団による行為で抵抗や拒絶が困難な状況であれば、「優越的な関係」と認定されることがあります。
2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えている
社会通念や業務目的に照らして「明らかに必要性のない言動」「業務の目的を大きく逸脱した言動」「手段や態様が不適切な言動」などが該当します。業務上の必要性がある場合でも、過度な量や内容、抽象的・画一的な指導はこの要件に抵触する可能性があります。
3. 就業環境が害される
精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させるなど、就業環境に悪影響を及ぼす場合が該当します。被害者の主観だけでなく、平均的な労働者の感じ方を基準に、客観的に見て「害されている」と認められる必要があります。
「不作為」もパワハラに含まれる
パワハラというと「暴言」「暴力」など積極的な行為を想像しがちですが、実は「何もしない」こと、つまり不作為もパワハラの一種となる場合があります。
無視や必要な指導をしないことは「不作為」
職場での「無視」や「業務上必要な指導・連絡をしない」ことは、積極的な行為ではなく「不作為」です。「言動」、つまりなんらかの行動がパワハラなのだから、不作為はパワハラにならないのではないか、と思われるかもしれません。
しかし、職場ではやらなければならない行為が、それぞれの責任としてはっきりしているのがふつうです。管理職の場合は、当然部下に指示を出したり指導することもそのひとつですね。それを行わない「不作為」は、部下を組織内のコミュニケーションから排除し、精神的苦痛を与える行為です。職場での行為について考える場合は、物理的な行動だけでなく、本来すべきことをしない「不作為」も含まれるのです。
例えば、部下が業務上困っているのに、上司があえて何も言わず放置したり、必要なフィードバックや指導をしない場合も「無視」と同様に、パワハラの一種とみなされることがあります。
暴力や暴言だけがパワハラではありません。「何もしないこと」、すなわち消極的な無視や放置もまたパワハラに該当する可能性があるのです。
不作為がパワハラとなる具体例
- 部下が明らかに困っているのに、上司が声をかけず、指導や支援を一切行わない
- 問題行動を繰り返す部下に対し、必要な注意や指導をせず放置する
- チームの一員として扱わず、情報共有や相談の機会を与えない
- 業務上必要な連絡や指示を意図的に行わない
これらは、本来ならすべき対応を怠ることで、部下の就業環境を害する場合、パワハラの3要件を満たす可能性があります。
「指導しない=パワハラ」になるかの判断ポイント
「必要な指導をしない」ことがパワハラに該当するかどうかは、前述の3要件をすべて満たすかどうかで判断されます。
1. 上司と部下の関係が「優越的な関係」にあたるか
管理職と部下の関係であれば、通常この要件は満たされます。
2. 「業務上必要かつ相当な範囲を超えている」か
業務上必要な指導を意図的にしない、または明らかに不適切な態度で放置する場合、この要件に該当します。部下の成長や業務遂行に必要な指導を怠ることは、管理職の職責を放棄する行為といえ、業務上の相当性を欠くと判断される可能性があります。
3. 「就業環境が害される」か
指導がなされないことで、部下が孤立感や不安を感じたり、仕事の進行に著しい支障が生じるなど、精神的苦痛や職場環境の悪化が客観的に認められる場合、この要件を満たします。
すべての「指導しない行為」がパワハラになるわけではない
管理職がうっかり指導を忘れた、誤解や行き違いで指導が遅れたといった場合は、パワハラの3要件をすべて満たすとは限りません。また、業務上の必要性がなく、指導の必要がない状況であれば、指導しないこと自体がパワハラにはなりません。
部下の自立を促す目的で一定の裁量を与えている場合や、段階的な指導方針に基づいて見守っている場合など、正当な業務上の判断であれば、パワハラには該当しません。
パワハラに該当しない場合でも管理職として不適切な行為
パワハラの3要件を満たさず、法的にパワハラとまでは言えない場合でも、管理職が必要な指導をしないことは、組織運営や人材育成の観点から極めて不適切です。
適切な指導をしない管理職のリスク
- 部下の成長機会を奪う:適切なフィードバックがないと、部下は自分の仕事に対する方向性を見失い、成長機会を逃すことになります。
- モチベーションの低下:指導やサポートがない状況では、部下の士気が低下し、離職率の増加につながります。
- 問題行動の放置:必要な注意や指導をしないことで、職場の規律や雰囲気が悪化します。
- チーム全体への悪影響:個人の問題が組織全体のパフォーマンスや文化に悪影響を及ぼします。
- 管理職自身の評価低下:マネジメント能力の欠如として評価が下がり、降格や配置転換の対象となる場合もあります。
組織としての対応
管理職が「パワハラだ!」と言われることを恐れて必要な指導を怠ることがないよう、組織として次のような対策をとりましょう。
- 管理職研修やフィードバックの仕組みを整備し、指導力向上を図る。
- 指導記録を作成し、適切な対応がなされているかを可視化する。
- 必要に応じて管理職の評価・配置転換・降格なども検討する。
- パワハラと適切な指導の違いを明確にし、管理職の不安を解消する。
管理職が果たすべき役割と適切な指導のあり方
管理職は「パワハラをしない」ことだけでなく、「適切な指導を通じて部下の成長を支援する」ことも求められています。パワハラを恐れて必要な指導まで避けてしまうのではなく、業務上必要かつ相当な範囲で、根拠と配慮をもって指導する姿勢が不可欠です。
適切な指導のポイント
適切な指導とは、次のようなものです。指導放棄ではなく、いっしょうけんめい指導している管理職も、実はひとりよがりな不適切な指導をしている可能性もあります。
ひとつひとつ点検してみましょう。
- 業務上の必要性を明確にする:なぜその指導が必要なのか、根拠を示す。
- 具体的で建設的な内容にする:抽象的な批判ではなく、改善点を具体的に伝える。
- 部下の立場や状況に配慮する:個人の能力や経験に応じた指導を行う。
- 継続的なフォローアップを行う:一度の指導で終わらず、進捗を確認し支援する。
部下の立場や状況に応じて、丁寧な説明やフィードバックを心がけることで、パワハラと指導の違いを明確にし、健全な職場環境を築くことができます。
まとめ
管理職が部下に必要な指導をしない「不作為」は、パワハラの3要件(①優越的な関係、②業務上必要かつ相当な範囲を超える、③就業環境が害される)を満たす場合、パワハラと認定される可能性があります。
「無視」や「指導しない」といった行為も、積極的な行為と同様にパワハラの対象となり得ることを理解し、管理職はパワハラを恐れるあまり必要な指導まで避けるのではなく、適切な方法で部下の成長を支援することが求められます。
たとえパワハラに該当しない場合でも、管理職として必要な指導を怠ることは不適切な行為であり、組織運営や人材育成に悪影響を及ぼします。管理職は、部下への適切な指導・フィードバックを怠らず、健全な職場環境づくりに努めることが重要です。